第11回 本の最小限の単位
![Photo by Amir Kuckovic[CC:BY-NC 2.0]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2014/03/dominick11.jpg)
“Minimum book” Photo by Zetalab[CC BY-NC-SA 2.0]
本を本として成立させる最小限の単位、とは何でしょうか。これは、ブログやネットメディアの連載記事といったひとまとまりの文章と、本として書店に並んでいるものの違いとは何かを考えることでもあります。
このことを実践的に考えるきっかけとなった企画として、昨年6月に刊行した電子書籍『オープン化する創造の時代』があります。これは角川グループのブックウォーカー社が手がけるカドカワ・ミニッツブックというレーベルから出版されたもので、このレーベルの本の特徴として「30分で読める」という点があります。日本人の平均読書速度として1分間600字程度という指標に基づき、およそ2万字以内のコンパクトな文章量で、価格も150円から300円と低く設定されています。複数の編集者の方に、新書や単行本のおおよその文字数が最低8万字程度と聞いたことがありますが、大体その四分の一ということになります。スマホや電子書籍リーダーで移動中や仕事の合間に読み、一回5分ほど時間を割いたとして、遅くても2、3日で一冊、早ければその日の間に読めるものです。
それでは2万字という文量が本の最小単位として妥当なのかどうか。実際に書いてみた経験からすると、ギリギリのラインで「これは自分が書いた本です」と主張できると感じました。例えば、この連載はだいたい2,000~3,000字ほどの長さですが、この連載記事が8〜10本ほど集まって一冊の本になると考えれば分かりやすいと思います。これが短過ぎるかというとそうでもなく、主張をコンパクトにまとめる分、逆にシャープにならなざるを得ないというメリットがあると思います。
このボリュームの電子書籍として比較できるのは雑誌記事の切り売りモデルです。たとえばWIRED誌は、雑誌一冊の他にも特集記事だけを99円で販売しています。そのトピックに時事性があれば、関心がある読者は一冊丸ごと購入する必要がないという消費者メリットもあります。書籍の場合も、数百ページを超える大著を数千円をかけて買って読み始めるのを躊躇してしまう場合、エッセンスを噛み砕いて圧縮した凝縮版が廉価に手に入れば、読者としても新しい作品をもっと手軽に発見する契機になるでしょう。
ミニッツブックで2万字の本を書くに当たって、
・コンセプトや構造を考えることに一番時間を割いた
・書き上げるまでの時間が短く、校正プロセスも速い
ということを感じました。この2点は、通常の8万字超の書籍の場合と比較して、両方とも出版社による編集の助けが大きかったこともあり、メリットとして捉えています。執筆開始から1ヶ月程度で原稿が書き上がり、その後1ヶ月以内に校正が終了し、その後数週間で刊行、というスピードもこれまでの紙印刷の書籍では体験したことのないスピード感でした。このレーベルの本が想定する読書スタイルも、執筆スタイルも、「可処分時間が少ない人」をターゲットとしていることが分かると思います。
当然、全ての本がこのようになればいいという主張ではありません。筆者が上梓した単著の紙印刷の2冊の本はどちらも20万字超ですが、長い時間をかけてリサーチや校正を繰り返し、事例や考察を十分に追加するというプロセスの中で全体の質を熟成させることができたと感じています。そして、その長いプロセス自体が筆者自身の学習を助けるというメリットが最も大きかったと思います。
対照的に、2万字の本という場合は、伝えたいコンセプトを最初に明確に設定せざるを得ないので、時間がない読者のために無駄なものをとにかく削ぎ落とすという作業になるのだと思います。当然、文字量の多い本の場合でも無駄なものを削ぐということは前提になりますが、想定する読者の読書時間が異なるというのが最大の違いになります。30分しか読んでくれないという場合と、3時間かけて読んでもらえるという場合では、本の構造が大きく異なるわけです。
そうなると、2万字の本というのは、短い時間で行うプレゼンテーションに近いものがあります。シンポジウムなどでは一人あたり10分、長い場合は30分という枠が割り当てられますが、その限られた時間のなかで考えを伝える。逆にいうと、深い部分には立ち入らないで、エッセンスだけ理解してもらえれば良いという割り切りが必要になります。研究者であれば学会発表、ビジネスの場面であれば企画のプレゼンといったシーンが似ているでしょう。
このようにエッセンスを研ぎすますというプロセスは、長い文章をまとめるという事とは別のベクトルでの学習効果をもたらすと思います。一言で自分が伝えたいことは何なのか、ということをまずは著者自身が問われるので、複雑な内容を簡潔に伝えるという知的労力を強いられるからです。反面、長い文章量のなかで様々な事柄についてじっくりと書く、ということは、どのようなコンセプトについて書くのかということを模索するプロセスにもなるので、理想的には、この二つのパターンを往復することが一人の著者にとってベストなのだと思います。
もう一つ、2万字サイズの書籍に関わることで見えたメリットとしては、8万字超の長い文章を書く時間や経験がない人でも、書き上げることが容易である、という点です。そして、一冊の本を書き上げたという実績を得ることで自信を得て、更に大きい書籍の執筆に挑む足がかりとすることができるでしょう。このことによって、潜在的な著者が顕在化し、書き手としての新しい才能の発掘にも繋がるのではないかと考えます。
ここで重要となるのが編集の役割です。文章が短いからといって、ただ埋めればいいというわけでは当然ありません。上記の書籍の場合は、ブックウォーカー社の編集作業の的確さと迅速さ、そして企画コンセプトの策定や販売戦略の明示化など、良い意味での従来の編集の役割が全うされているからこそ、「本」として成立していると思うわけです。
次回では、本の最小単位から編集の役割を考え、オープン出版の事例をヒントに本のソーシャルな編集と受容の新しい形を模索したいと思います。
[読むことは書くこと Reading is Writing:第11回 了]

読むことは書くこと Reading is Writing:第10回「本の死とその蘇生」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.








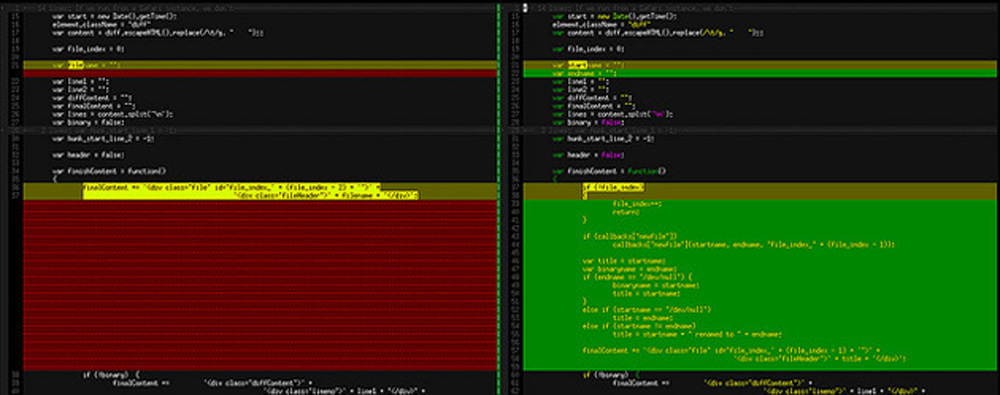



COMMENTSこの記事に対するコメント