第12回 「助産術としての編集とそのオープン化」
![“Eggistentialism 1.5 or Three of a Perfect Pair” Photo by Mike Bitzenhofer[CC BY-NC-ND 2.0]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2014/04/dominick12.jpg)
“Eggistentialism 1.5 or Three of a Perfect Pair” Photo by Mike Bitzenhofer[CC BY-NC-ND 2.0]
ある作品をオープンにするということは、権利を他者に対して開いておくという意味の他にも、敷居を下げることでより多くの人が参加しやすくするという、より広い意味として捉えることもできます。その意味でも、オープンかクローズということは、0か1かという二値的なものではなく、0%〜100%というような度合いとして捉えた方が良いでしょう。
たとえば著作権の話でいえば、クリエイティブコモンズのようなオープンライセンスが普及する以前でも、利用者が著者や権利者に直接連絡をとって許諾をもらえば、合法な二次利用は可能でしたし、著者や権利者も、独自の二次利用許諾の規約を作れば、それを許可することが可能でした。オープンライセンスがもたらしたものは、この許諾申請や規約作成のステップ数を減らすことにより、法律に詳しくなくても非常に簡単に合法的な二次利用を行ったり許可することを可能にしたということです。
前回の2万字という本の最小単位という話でも、短い本の目安としての新書の8万字と比べて4分の1という短さにすることによって、書き手と読み手双方の敷居を下げられるメリットがあるということを述べました。それだけでは文量の話だけですが、一番重要な側面は、より多くの潜在的な著者が「プロの編集サービスを享受する」という体験を得られる可能性だと考えています。なぜなら、現行の出版界の仕組みでは、編集サービスの恩恵を受けられる人の大半は、全体から見たらほんの一握りのプロの作家や既に著名な人間に限られていると思うからです。出版という業態そのものを個人に対してもオープンにするということを考えるならば、編集体験をより多くの潜在的な著者が受けられるようにする仕組みを考えることは有効ではないでしょうか。
以前、友人に「知人が本を出版したがっているのだけど、どうすればいいですか?」と聞かれて返答に困ったことがあります。というのも現行の出版界の常識では、無名の著者による持ち込み企画というのはよほど内容の質が高いものではない限り、実現するのはなかなか厳しいのではないかと思ったからです。というのも、紙媒体の場合は特に、出版から流通に至るまでのコストが高いので、無名の著者にかける編集コストと事業リスクが見合わないのではないかと思うからです。逆に電子書籍の場合は諸々の物理的なコストをカットできるので、逆に出版社としてもより低リスク、低コストで新しい著者を輩出することが可能でしょう。それにしても、編集者が担当に付いて編集や連絡の稼働を担保するにはお金と労力がかかります。
筆者自身の経験でいうと、幸運にも様々な雑誌媒体で原稿を書かせてもらったり、活動をプレゼンテーションする場を多く頂いたりする中で編集者の方たちからお声をかけて頂いて、これまで単著を書くという機会を数回頂いてきました。なので、自身の著作を世に問うということは確率論的に幸運なことであるという認識と同時に、その分重責を伴う作業なのだという感覚があります。
単著を書くという過程で学んだこととしては、原稿を一本書くことと、本を一冊書くことでは、体験の質が圧倒的に異なるということでした。最大の違いの一つは編集者との中長期的な対話だと思います。
哲学者プラトンは自身の師であるソクラテスを助産師として描きました。いわく、ソクラテスは人々の対話を通して、母親が子供を産む際に助産師が手助けをするように、一人の人間が自身の意識の中で胎動している秘められたアイデアや考えの塊を「表現」として外部化することの手助けを行っててきたというわけですが、筆者はこのことこそが編集者の最大の権能なのではないかと考えています。
編集者(という役割を受け持つ人)は、自分で表現するわけではありません(厳密には、編集行為そのものも一種の表現ではあると思いますが、ここではまずは著者という位相に注目するために割愛します)。子供を産むのが必ず母親であるように、作品を産むのは必ず著者です。しかし、自分が書こうとしているテーマへの関心を共有する優れた編集者としての対話を通して著者自身の内部で隠れている気付きを外部化するプロセスを経て、初めて混沌とした考えが秩序づけられたり、よりよい形で表現されたりするという経験は多くの著者が経験していることではないでしょうか。
余談ですが、このことは本を書くことに限定されない現象ではないかとも思います。何かを特定の形式で表現しようとしている時、他者と対話することによって初めて適切な形を与えられるアイデアが産まれるということは、様々な領域で起こっていると思います。当然、この他者との対話というプロセスを必要としない、いわゆる天才的な人も少なからず存在しますが、そういう人たちも自身の考えを意識の中で外部化して観察し、フィードバック回路を作り出すという一種の仮想的な対話を行っているのではないかと筆者は憶測しています。
それではなぜ対話を行うことによって考えが「助産」され得るのでしょうか。それは対話が、最も基本的で原初的な表現の形式だから、だと言えるでしょう。編集者が発する問いや応答によって、著者が表現しようとする事柄の方向性と射程が徐々に狭まり、著者の意識のなかで潜在していた表現に輪郭が与えられる。そのことによって、対象のテーマに関する著者の解像度も高まり、新たなアイデアや表現が連鎖的に編み出される。
このことは、スポーツ選手に例えると、専属のコーチがついてトレーニングを指導してくれるのか、自力でトレーニングプログラムを組んで練習するのか、ほどの違いがあると思います。コーチ=編集者とは、自分を常に客観的に観察して、適切なフィードバックを返してくれる存在であり、その「機能」を天才のように内蔵することのできない多くの人にとっては、いま行おうとしている表現の質を高める上でも大変貴重な存在でもあると言えるでしょう。
ITを用いた出版のオープン化ということを突き詰めて考える時、優れた制作/編集ツールや出版ツールに個人もアクセスできるようにするということ以外にも、編集者やそれに準じる他者との対話プロセスという、出版界やアカデミア(学術論文の査読というのも近似するモデルとして見て取れるかと思います)が長い年月に渡って培ってきた機能的文化をより多くの人に提供する、ということもまた必要なのではないかと考えます。
次回は、潜在的な著者と潜在的な担当編集者をオンラインでマッチングさせる未だ見ぬサービスの有り様を、WikiやGitといったコラボレーション技術の本質と共に素描してみたいと思います。
[読むことは書くこと Reading is Writing:第12回 了]

読むことは書くこと Reading is Writing:第12回「助産術としての編集とそのオープン化」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.








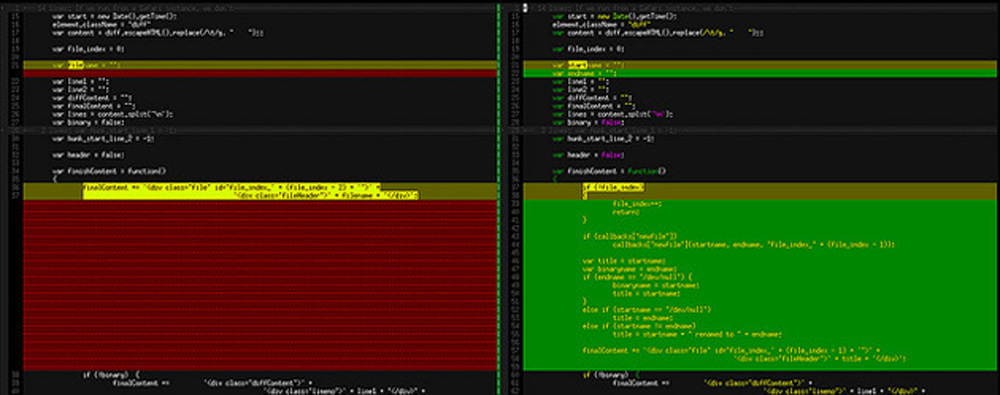



COMMENTSこの記事に対するコメント