第8回 読み手と書き手の非対称性①
![“Greater Chicago Metropolitan Area (NASA, International Space Station, 02/02/12)” by NASA's Marshall Space Flight Center[CC:BY-NC 2.0]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2014/01/dominick08.jpg)
“Greater Chicago Metropolitan Area (NASA, International Space Station, 02/02/12)” by NASA’s Marshall Space Flight Center[CC:BY-NC 2.0]
前回の記事で言及したように、視線追跡技術を活用して読む行為を精確に記録できるようになれば、これまでは受動的だと思われていた「読む」という行為を、書き手の執筆行為に影響を与えるフィードバックとして捉えることが可能になります。このことは、読み手が書くプロセスに参加するための最もローレベルな方法だと言えるでしょう。そのように考えたとき、読者はただ読んだり、自分の備忘録やメモのためにハイライトしたり、コメントを書くだけで、著者の創造性に寄与することになります。この考え方は、あるプログラムの利用時に、不具合を起こした際にレポートが送信されることを許可するということに近いでしょう。
もしくはプログラムの不具合報告をメールや送信フォームから送るということと同様に、電子書籍リーダーの中で誤字脱字をハイライトするだけで指摘するアクションが用意されていれば、多くの有効な指摘を行った読者に何らかの特典や報酬を還元するというようなことも可能になります。当然、書籍の場合もプログラムの場合と同様に、読書ログを記録されることに対して読者がオプトアウトできるようにするべきでしょう。しかし、読者も本の改善や著者の成長に寄与しているという意識が生まれるようにサービスやアプリケーションを設計することによって、オープン出版やオープンソース型ソフトウェア開発における参加の楽しさや社会的な利益の達成といったメリットを読者が享受できるようになると考えられます。
また、視線追跡などによって精確な読書量の把握が可能になれば、新しい本の課金方法も実装可能になるでしょう。たとえばRead Petite *1という未公開のサービスでは、月額課金で書籍の読み放題を実現する予定ですが *2、文字単位での読書量が仮に把握できれば、著者への印税の支払いから読者からのサービス料の徴収までが読まれた文字数に応じた従量制にすることが可能になり、本を巡る新たな商慣習の提案につながるのではないでしょうか。これまではダウンロードされたか否かという低い解像度で書籍の利用を計測し、対価の支払いを計算させてきたわけですが、いわゆる「積ん読」本のように読者の本棚や電子書籍リーダーで詰まれたままで読まれてない本も大量にあるとすれば、より公正に「読まれた本」を特定し、その著者に正当な対価を支払えるようになるでしょうし、読者に対してもまた、実際に読んだ分だけ課金されるという新しいメリットを提供できるでしょう。
このような読書形態が広まれば、本のダウンロードは基本無料で、読まれた分だけ課金されるという解像度の高いフリーミアムモデルが生まれるかも知れませんし、著者と読者それぞれに最適化した読書ログの解析ビジネスも発展する余地が生まれます。読者にメリットのある読書ログの解析方法としては、ログを学習記録に活用する学習支援サービスや、より精確なレコメンデーションサービスなどが考えられます。
繰り返しますが、読書ログの精緻化は読み手を書き手とつなげる最も低次元の方法だといえます。それは読むことの創造性を喚起し得るかもしれませんが、このシナリオでは読み手の「読むという行為」をコンピュータを用いて自動的に記録するので、読み手はあくまでも受動的な存在のままです。そこで読み手が能動的に「書く」ものといえば、メモやハイライトやコメントといった極々短いものでしょう。そこから、「一冊の本の著者」になることには依然、大きな隔たりがあります。
私がどうして「一冊の本の著者」にこだわるのか、それは「作品」を作り、世に問うということがその作者にもたらす(金銭ではなく、経験としての)利益が重要だと考えるからです。ここでいう「本」とは、ある文章の集積が作品たりえる最小限の単位であり、その制作を行う人を「書き手」と呼んでいます。そして、この読み手と書き手の非対称性を埋めることにこそ、オープン出版に限らず、あらゆるオープンコンテンツ運動の本質的な理念があるのではないかと考えます。
ある作品が利用者のフィードバックを間断なく受け続け、恒常的に更新され続けること。「読むことは書くこと」の実体は、このように表現することができるでしょう。この図式はどのような表現形式における「作品」の生成プロセスにも当てはめて考えることが可能です。文章、音楽、映像、美術などのいわゆる文芸的な作品もそうですし、ある対象物を成立させる核となる個人や集団のプロセスが存在し、かつその対象物を利用する個人や集団が存在するようなあらゆる領域にも適用して考えることができます。たとえば会社や教育機関、政府や政治運動といったサービスを提供する組織全般に対しても考えられるでしょう。この観点は、表現という行為を、その具体化の方法や発現する効果が何であれ、コミュニケーションとして捉えるものです。そして表現を行う主体を含めて、コミュニケーションのプロセスを一つのシステムとして観察することで、異なる表現様式を同一の基準で比較できるようになります。
多様な表現の各論に入れば、作品の様式、利用の方法、フィードバックの形態、更新の手続きといった個別のプロセスがそれぞれ異なります。これらのプロセスは手段であっても目的ではないので、ネット以外の方法論を用いて考えることは当然可能ですが、この連載では主にオープン出版とオープンソース開発というネット上で観察できる「読むことと書くこと」の事例と「本」というメディウムの更新の接続を考えているので、ソフトウェアにおけるオープンソース型開発や、それに構造が近似する書籍のオープン出版についてこれまでも言及してきました。
それはソフトウェア開発が、コミュニケーションコストがゼロに近づけるインターネットというインフラと親近性が高いからだと言えます。当然ですが、ソフトウェアを成立させる資源はデジタルなコードであり、ソフトウェアが作動する場もデジタルな環境なので、物理的な形に落とし込む中間プロセスが不要である点が、オープンソース型開発が開花するための前提条件であったと言えるでしょう。オープン出版もまた、デジタル形式で書籍のソースを利用可能な形で公開することで、本が著者や出版社以外の読者によって他言語に翻訳されたり、校正されるといった状況がネットを介して生まれてきました。
次回は、オープン出版とオープンソースソフトウェアの比較を通して、文章とプログラムというメディアの本質的な差異を浮き彫りにして、本という作品の制作により多くの読者が関わるようになるための条件について考察していきます。
[読むことは書くこと Reading is Writing:第8回 了]
注
*1│Read Petite:
URL: http://readpetite.com/
*2│月額課金で書籍の読み放題を実現する予定:
“Prepare Your Eyeballs: E-Book Subscriptions Are Coming”,
URL: http://www.wired.com/gadgetlab/2013/04/e-book-subscriptions/

読むことは書くこと Reading is Writing:第8回「読み手と書き手の非対称性①」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.








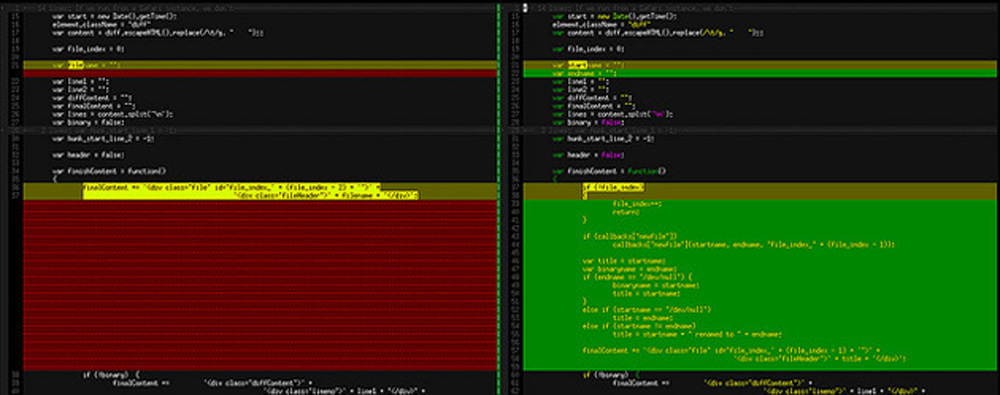



COMMENTSこの記事に対するコメント