第3回「遺言」
水野祐
遺言を作成する作業は、自らの死後を「編集」し、「デザイン」する作業である。
そのように意識するようになったのは、ある依頼者の遺言を作成する仕事を通してであった。その依頼者は社会的な名声やお金もあり、遺言を作成するには歳もまだ若かった。大病を患っていたわけでも、死期が迫っていたわけでもなく、これから相続人が変わることだって十分にありえた。しかし、彼女は、いつ訪れるかわからない自らの死後について他ならぬ誰よりも興味をもっていた。それは彼女がアーティストであり、50年、100年先をみて、自らのクリエイションを考えていたからなのかもしれない。
ここで遺言について少し解説すると、遺言とは、形式や内容にかかわらず、広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多く、「遺書」という言葉も同じ意味でよく使われる。このうち民法に定められている法制度としての「遺言」は、故人による死後の法律関係を定めるための最終の意思表示をいう。そして、法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければならない(これがけっこう厳格なのである)。ちなみに、この法制度としての遺言を、法律家は「いごん」と読むことが多い(本当に法律家っていうのはクソだと思う)。
先の依頼者も、遺言作成にあたり、自らの財産としてどのようなものがあるか整理し(預金がどこ銀行にいくらあるとか、不動産はなにがあるとか)、それらをどの相続人にどう分配するか、という通常よくあるオーダーもあるにはあった。しかし、彼女のオーダーがとりわけ特徴的だったのは、「私が死んだら、作品(の現物)以外の私が生きていたという証を削除してほしい」というものだった。特に彼女が気にしていたのは、インターネット上に溢れる彼女の作品の画像やポートレート、インタヴュー等だった。これは、現在欧米などで盛んに議論されている「忘れられる権利」などと呼ばれているものだが、まだ権利として認められるに至っていない。すでに述べたとおり、法制度としての遺言はあくまで「法律関係」を定めるための意思表示なので、それ以外の要望等は法制度としての遺言には含まれず、法的な効果は生じない。たとえば、「息子●●に、この土地を相続させたい」は法的な意味での遺言になるが、「骨は海に撒いてくれ」はそうではない。かくして、彼女の一風変わったオーダーは遺言として法律的な効果が生じることはなく、「付記事項」として遺族に対する「お願い」「メッセージ」として記載されるにとどまることになったのだが、この「お願い」「メッセージ」には法的な拘束力がないので遺族は守らないことも可能である。しかし、上記特殊なオーダー以外にも彼女の自らの死後に対する想像力やこだわり、備えは死をネガティブに捉えるのではなく、それを人間関係やもっと言えば社会を整理する1つの契機としてポジティブにも捉えているようにぼくには思えた。そのような彼女の死に対するまなざしは、これまでネガティブにしか考えていなかった遺言作成という行為を、死後を「編集」し「デザイン」する行為へと捉え直すきっかけとなった。
また別の例を挙げるのであれば、伊丹十三監督の処女作『お葬式』は、葬儀というタブーを批評的に映画というエンターテインメントの素材として再構成した傑作であったが、この作品には死というものを「編集」し「デザイン」する視点も含まれていたように思う。この作品において、伊丹は自らを投影した主演の山崎努に、「俺が死ぬときは、桜が満開のときに死のうっと」とつぶやかせている。すでに述べたとおり、これも当然のように法的な意味での遺言にはなりえないのだが、伊丹ほどの様式美を重視する人が、自分を投影した山崎努にこのようなセリフをつぶやかせておいて、これを貫徹しないわけがない。なので、ぼくは12月に死んだ伊丹が自殺だったわけがないと個人的には思っている。
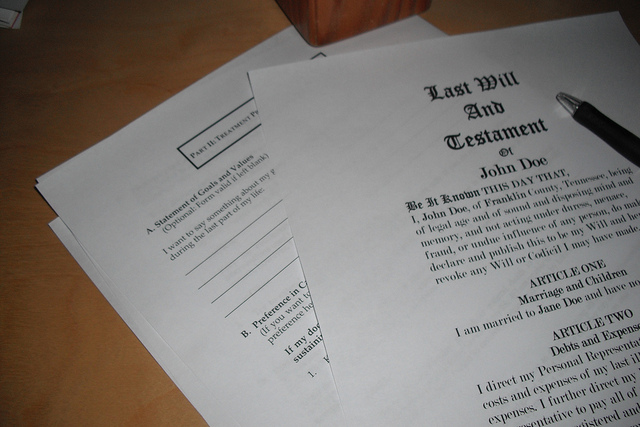
Last Will and Testament / Ken Mayer CC BY Some Rights Reserved.
大きく逸れた話を元に戻すと、弁護士の仕事には、遺言の作成とか、遺言執行人としての業務、遺産分割調停や遺留分減殺請求など相続に関する紛争の解決というものがある。相続人たちは、故人が遺した遺産の大小を問わず、親族内で骨肉の争いを繰り広げる。家父長制があったせいで、殊に日本では世間一般の認識と法制度に乖離が大きいことから、この争いが長期化かつ激化しがちである。そして、なによりこの争いは無駄が極めて多く、不毛である。しかしながら、故人が生前に自らの財産等の整理を行い、法制度としての遺言を作成し、財産の分配について決定しておけば、この争いは相当程度避けることができる。遺言を作成する意義はまさにここにある。
この不幸で無駄の多い争いに触れるたびに、自らの死後を「編集」し「デザイン」する志向がより広まり、誰もが遺言を作成しておく世の中になることを願わずにはいられない。このような不毛な争いを避けるために、ぼくは、成年に達した日本国民に、財産目録と遺言の作成を義務付けることを提案したいくらいだ。別に第三者に対し公開する必要はない。ドナーカードのように隠し持っていればいい。この2点を義務付けることで、遺産をめぐる不毛な争いの多くは回避され、人はより多くの時間と労力を別の生産的な事柄に割くことできるようになるだろう。そういえば、2011年の映画『エンディングノート』(砂田麻美監督)により「エンディングノート」という習慣が社会的認知を得たが、自らの終末期に備えて希望を書き留めておくこの習慣は、上記提案と同じ方向性を志向するものなのかもしれない(一方で、法的に拘束力のない1枚のメモが遺族による紛争を激化させることもままあるので、慎重な判断が求められる)。
人はなぜ遺言を作成しないまま死んでいくのか。死後の「編集」や「デザイン」はなぜ難しいのか。それは死に対するぼくらの畏れ故なのかもしれないし、死後の状況に対する想像力の欠如のせいなのかもしれない。今回の記事では、そのような人の「弱さ」やそれにより死後に生じる負の連鎖を断ち切るために、死後を「編集」し「デザイン」するという思考を提案させていただいた。なお、遺言は英語で「a will」とか「last will」とか言われる。これは欧米では遺言により未来を「編む」という思考がより一般化しているということなのだろうか。
実は、死後を「編集」し「デザイン」するという思考が大事なのは、なにも生身の人間にかぎったことではないのだが、それについてはまた次の機会に。
[Edit × LAW:第3回 了]

Edit × LAW③「遺言」 by 水野 祐、Tasuku Mizuno is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.











COMMENTSこの記事に対するコメント