池田剛介+寺井元一
「アートと地域の共生をめぐるトーク」
松戸駅の半径500メートルを「MAD City」と名付け、アーティストやクリエイターを誘致してまちづくりを行う「まちづクリエイティブ」(以下、まちづ社)の代表・寺井元一さんと、MAD Cityにアトリエを構えている美術作家・池田剛介さんによる、まちづくりとアートをめぐるトークをレポート。池田さんがMAD Cityの公式サイトで連載している「アートと地域の共生についてのノート」や具体的な事例をもとに、アートがまちづくりに関わっていく可能性について、議論が交わされました。
●本記事は、2015年5月29日にFANCLUB(松戸市)にて開催された「池田剛介+寺井元一 アートと地域の共生をめぐるトーク」を採録したものです。なお池田さんは現在、台北での滞在制作を行っており、その経緯は「アートと地域の共生についてのノート(台湾編)」にて掲載中です。
●連載「アソシエーションデザイン つづく世界のつくり方」本編はこちら。
【以下からの続きです】
前編:「行政側は『市民参加』という旗印を掲げるけれど、その実あまり市民参加を望んでいなかったりする。」
[中編]
アートよりも「コミュニティデザイン」のほうが効率的だとしたら
寺井:一方で、「リレーショナル・アート」っていう、コミュニケーションをもっと図ろうみたいなことが地域のアートプロジェクトですごく重宝されているっていう話がある。山崎亮さんはまちづくりの人で、「ワークショップをやる人」っていう印象が強いかと思うんですけど、瀬戸内国際芸術祭とかになると山崎亮さん自身もアーティストの一人として迎えられて、実際にワークショップをモチーフにした作品を作っている。そうなってくると、結局アーティストと山崎亮さんの違いって何なのかとか、山崎さんのほうがワークショップはうまいんじゃないの?とか、そうするとリレーショナル・アートって山崎亮さんがやってることと何が違うの?などといった議論も生まれる気がしています。
池田:アーティストがワークショップをするよりは山崎亮さんにやってもらったほうがいいんじゃないのっていう気持ちもありますよ、本当を言うと(笑)。そこで重要なのは、どのようにプロジェクトの中に連続性を作っていくかっていうことになると思います。
寺井:さらっと凄いこと言いましたね(笑)。「連続性」というのはどういう意味合いなのか、もう少し聞かせてもらえますか。
池田:個々の住民レベルからより大きなプロジェクトに至る道の連続性。たとえば國分さんのエピソードでは、道路という公共的なプロジェクトが住民側と断絶してしまっているように見えるわけです。そうではなく、住民と公共的なレベルの物事を、なんらかの仕方で地続きにしていく必要があるだろう、と。

寺井:(公共的なプロジェクトになりうるまでの)道がつながっているかいないか、みたいな感じですか? 抽象的な言い方ですけれど。
池田:そうですね。先の説明会の話には断絶を感じます。それに対して参加者からのボトムアップによってコミュニティを作っていく、というのが山崎さんの実践。地方のアートプロジェクトなどで求められているものも、こうした連続性と関わっている場合が多くて、それこそアートプロジェクトとかに参加者が入っていってコミュニティによる作品ができましたとか、和気あいあいとした人間関係ができました、みたいな。でもそれって山崎さんの方がよっぽどうまくやれるわけでしょう。まちづくりとかコミュニティづくりという目的に対する社会的有効性でいうと、おそらくアーティストがアートプロジェクトとしてやるよりも、むしろデザインとして山崎さんのような人にやってもらったほうがいいんじゃないか。それはアートではなくデザインの領域だと思うんです。
実を言いますと僕は学部生のころデザイン科出身で、広告なんかを勉強する学科にいたんです。そこで何が重要かというと、モノとしてのポスターやらプロダクトを形作るということではなく、クライアントと消費者の間をどういうふうにつないでいくか、ということです。クライアントの要望があり、消費者との間に入って、その間の連続性を作っていく。こういうことをデザインの仕事として学びました。といっても僕はほとんどデザインの世界に関心を持てなくなっていたので、完全に途中からドロップアウト状態でしたが(笑)。
これまで言ってきたように、コミュニティデザインの必要性についてはよくわかるわけですが、じゃあそこでアートはどうすればいいのか、アートの位置付けについて改めて考えてみたいと思うわけです。
寺井:まちづくりとかデザイン、それから地域アート、リレーショナル・アート、地域アートプロジェクトが近づいていって、その役割分担というか有効性を考えたときに、僕自身もアーティストが参加するのがすばらしいっていうのは本当なのかって思う瞬間があったりします。「アートは何ができるのか?」ってことを、アート側も考えなきゃいけないという気がするんです。
アートの持つ「中断」作用とは
池田:いろんなところで芸術祭などが乱立していく中で、コミュニティデザインで行われていることを踏まえながら、アートが持つ意味をもう一度問い直すべきではないかと思います。
それを考えていくためのヒントとして、連載の中ではフランスの哲学者ジャック・ランシエールの議論に言及しました(「アートと地域の共生についてのノート」第4回)。政治や美学に関する著作で知られる哲学者ですが、欧米圏で90年代以降たくさん出てきたような「関係性の美学」や、その周辺に見られる、社会に直接的に関わっていくような傾向のアートを批判していて、アートは直接的に社会に対して働きかけるものではないんだ、ということを言ってるんですね。その中でたとえば「パラドキシカルな有効性」という言葉を使っていて、これを言い換えれば「非有効的な有効性」となるかと思います。
寺井:コミュニティデザイン的なものは、わかりやすく「有効な有効性」ですよね。
池田:そうですね。それに対して「非有効的な有効性」、つまり有効でないことが有効であるということ、これがどういうことかちょっと考えてみたいと思います。同じような文脈でランシエールが言ってるのは、作品と受け手(見る側、鑑賞者)との間に、ある種の中断が起こる、中断の作用ということです。
寺井:「非有効的な有効性」っていうのは、「中断」と呼べるものかもしれないよ、ってこと?
池田:そうです。「中断」、つまり連続性が途切れるということと「非有効的な有効性」とがどのように関わるのかを考えてみたいと思います。
デザインってクライアントから仕事を受けて「こういうふうに売れますよ」とか「社会の中でこんなふうに有効に働きますよ」とか必ず示さなくちゃいけない。僕の理解では、コミュニティデザインもおおよそ連続性に関わるもので、ワークショップなどを通じて参加者同士の関係性を生み出しつつ、地域レベルのプロジェクトへの連続性を作っていく実践なわけです。
それに対してアートは「中断」に関わるものであると考えてみたい。先の例のように、住民と行政との間の断絶が一方にあって、他方でスムーズにそれらをつなげていくような「連続性」があるとすれば、その間のどこかに「中断」というものを考えることができるのかもしれない。
別の角度から言うと、アートって美術館やギャラリーの中にあって、なにか崇高で手の届かない、よくわからないものとされている面もありますよね。
寺井:一方でアート業界の中では、「アートがわからないって言う人がいる、でもそれはしょうがないじゃん」みたいな感覚もありますよね。
池田:「アートはよくわからない」「わからなくてもいい」っていう言葉も、断絶のひとつのあり方でしょう。一方でこうした断絶があり、他方ではそれを社会に対して開いていくべし、という連続性への志向がある。おそらく「中断」っていうのは、その中間にあるものではないかと思います。
ひとつ例を挙げると、経験ある人も多いのではないかと思うのですが、マンガとか映画とか何でもいいのですが、最終的にハマるものって始めは何だかよくわからないものだったりしますよね。最初は何か引っかかりがあるっていうか、何が面白いのはわからないのだけど、それを何度も咀嚼しているうちに面白くなっていく、みたいなことです。
「中断」という作用は、そういう経験と関わっているんじゃないでしょうか。最初にちょっと距離があって、作品との関係がスムーズに連続したものではない。だけどしばらく作品を読み込んでいく中で、なんだか面白く感じられるようになっていく。そもそもなぜそういう中断が起こるのかというと、おそらくそれは、作品の中にある「論理のようなもの」がわかりづらいからだと思います。でもそれが何かしら独自の論理で作られているとすれば、それを自分なりに読み解けるようになってゆき、その作品を学んでいくことになる。それはほとんど知らない語学がわかるようになるとか泳げるようになるとかの経験に近い。そういう経験の出発点となる「中断」の作用がアートにはあるんじゃないかと考えてみたい。
寺井:アートの展覧会や作品で、そういう中断効果というか、「非有効的な有効性」があるんじゃないかって池田くんが思う事例は具体的にありますか?
池田:ついこの間まで京都で「PARASOPHIA(パラソフィア/京都国際現代芸術祭2015)」という国際芸術祭が行われていたのですが、「崇仁地区」というエリアで、ベルリン在住の2人組、ヘフナー/ザックスというアーティストが《Suujin Park》というプロジェクトをやっていました。そこは京都駅のすぐ近くにある、ものすごく大きな被差別部落の地区なのですが、なかなか複雑な人間関係や政治的な関係もあって手が出せないような独特のエリアになっている。世界有数の観光都市の玄関口のすぐそばに日本最大級の被差別部落があるわけです。

ヘフナー/ザックス《Suujin Park》(2015年)
(「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015」のFlickrより/CC BY-NC-ND 2.0)
ヘフナー/ザックスはその崇仁地区にある様々な遊具や植物、その他のオブジェクトなどを集めてきて、それらを新たに再構築しています。もともとこの地区には、建物が壊されたけど新たに建てることもできず空き地になっているエリアがたくさんあって、おそらく不法滞在できないようにということだと思うのですが、フェンスで囲まれている空き地が点々としているんですね。タイトルによれば「公園(park)」ということですが、「そこで遊ぶことができますよ」とか「みんなで作りましたよ」といったような連続性ではなく、フェンスで囲われていることが一定の隔たりを作り出していて、それが中断の作用に関わっているように感じられます。

ヘフナー/ザックス《Suujin Park》(2015年)
(「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015」のFlickrより/CC BY-NC-ND 2.0)

ヘフナー/ザックス《Suujin Park》(2015年)
(「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015」のFlickrより/CC BY-NC-ND 2.0)
フェンスに囲まれた空き地には、大きな石が無造作に置いてあるように見えます。一見すると何かよくわからなくて作品と気づかないかもしれないですが、よくよく見てみると棒みたいなのが突き出していて、石がポンポンと半円状に一定の間隔で置いてあって、影ができて……これが日時計のようなものであるとわかります。あるいは小さな川のほとりに壊れたまま放置された電灯があり、川に置いた自転車の前輪がまわって発電することで自転車のライトが光っている。もちろんそれは実際の社会的な有効性をもってライトが機能するわけではないから非有効的なんだけれど、でも同時に、普段だったら全然気付かないようなものに目を向けさせるようなものでもあるんですね。
おそらくパッと見ただけでは、この作品の面白さはよくわかりません。だけどフェンス越しにじっくりと見ているうちに、その作品のなかにある「論理のようなもの」や、あるいはそれが置かれている環境についても考えさせていくようなものになっているわけです。

壁画プロジェクトがもたらした「中断」
池田:ひとつ京都の例を出したんですけど、寺井さんにも聞いてみたいと思います。松戸では2010年に“MAD WALL” Projectというものをやっていたと思うんですが、僕の友人の大山エンリコイサムさんとか、他のグラフィティアーティストの、3人くらいでやったんですよね?
寺井:そうです。場所は根本っていう地区の陸橋の擁壁ですね。もともとの絵が30年くらい前のもので汚くてイヤだと町内会の人が不満を持ってて、きれいにするだけじゃなくてプラスになるデザインのようなことをしてほしいと。そのタイミングで大山エンリコイサムからZEDZっていうグラフィティアーティストが日本に来るから何か一緒にできないかっていう連絡をもらって、間をつなぐみたいなことをやったんです。

“MAD WALL” Projectにおける、ZEDZ・大山エンリコイサム・MHAKによる壁画アート作品(2010年)
池田:そのときに大山さんから、作業をしていてすごく反響があるという話を聞いていました。これって別に、何かワークショップをしながらこういう絵柄にしようとか、アーティストをみんなで選んだり、みんなが参加して描いたりしたわけではないんですよね?
寺井:実はこれは翌年に裏側の擁壁で2回目をやっていて、2回目は結構そういうことをやっているんですけれど、僕にとっては1回目と2回目で違うやり方に関わったわけで、いろいろと思ったことはありますね。確かに、1回目は池田さんの言うようなやり方で、ワークショップ的なことはなかったです。
池田:ワークショップや話し合いのような、いわゆる参加のようなことをせずに行ったことが良かったんじゃないかと僕は思っていて。おそらくこれもある種の「中断」の作用と通じてるんじゃないかと思うんです。自分たちの慣れ親しんだ場所でなんだかよくわからないことが起こっているぞ、と。こうした中断を経て、「何やってるんですか?」って聞いてみたり、何か差し入れを持っていったりとか、そういうことが起こったんじゃないかっていう気がします。
寺井:今でも覚えている好きなエピソードがあって、毎日現場に「寒いだろ」みたいな感じでコーヒーを差し入れしてくださる地域の方がいたんですね。高齢の方で、その人が毎日のように行きつつも「絵が全然わかんない」と思っていたらしくて、アーティストに聞いても抽象的な絵だしやっぱりわからないと。それでも毎日行って差し入れしていると、絵が毎日違って見えて、好き嫌いがなぜかある、と気づいたらしいんです。
それで最終的に、そこに何が描いてあるかという客観的な事実ではなくて、その絵を見た自分がどう感じたかという主観的な出来事のほうが重要なんだ、と。毎日コーヒーを淹れに行ってるうちに、絵は自分の外にあって正解があるんじゃなくて、外にある絵に対して何か感じることで、自分の心のうちを認識することができるのが素晴らしいと思ったという、そんな話をされたんですね。

結構こういう絵(グラフィティ)って抽象的だから、「意味がわからない」って言われたりもするんですよ。だからやめろっていう話もあるし、ワークショップで「次の絵はもうちょっとわかりやすく……」とか言われたり。でも、そのおじいちゃんが「絵のことがなんかわかったぞ! これからいろんな絵が見たいなぁ」みたいなことを言ってたのを覚えていて、僕にとっては地域とアートの関わりという意味で、すごく可能性を感じた瞬間でした。ただ、例の壁画って、いいことだけじゃなくて不評だったりもするんですよ。エンリコの作品の横を歩いていくと、子どもがいつも泣くっていう人がいる(笑)。むちゃくちゃ泣いちゃって、どうしてくれるの?みたいな苦情があるんです。僕はそれを聞いたとき、すごくいいことだなと思いました。この絵によって自分の何かが変わっちゃうような人がいる、それってある意味正当な理解というか、「中断」の話に近いのかなって。
池田:僕もそれはいい話だと思います。泣くというのは対象との間に何かしらの感覚的な切断というか、異質なものだと感じられているからだと思うんですね。それは普段僕らが持っている感性とか、日常的に作り上げている世界に対して揺さぶりがかけられている状態なわけでしょう。だからさっきの話で、見るたびに絵が違って見えるっていうのも、それは見るたびに違うものが作品から引き出されてくるということですよね。1回見て「はいわかりました」っていうものであれば、何度も見る意味がないので、むしろ汲み尽くせなくて感覚の隔たりがあるからこそ何度も見ることができるし、その都度に新しいものとして見ることができる。
寺井:難しいと思うのは、「子どもが泣いちゃう」っていう話は結構好きなんだけど、行政や地域の多数決的な世界だと、その出来事は良い、とは結論されないんですよね。むしろそれは良くないっていうことにどうしてもなっちゃうし、僕が「これでいいんだ」って言っても通らない悩ましさみたいなのは感じますね。
池田:そこは確かに難しい問題ですね。「中断」というのは、別の言い方をすると、あるものがどのように受け取られるのか、あらかじめ決められないということ。たとえばデザインだったら「こういう人に買われますよ」といった社会の中での着地点を説明しなくちゃいけない。それはまちづくりの場合も同じだと思いますが、デザインをしていく上ではプロジェクトの社会的な位置づけを考えなくちゃいけないわけですよね。
逆に言えば、それがどこに向かうかわかってしまうと中断にならない。だから、それを見た人が結果としてどうなるかわからない「非有効性」をどう捉えていくのかが難しい部分になるのでしょう。でもそれを予め設計することはできないし、むしろ設計できない出来事にどのように逢着することができるのかが重要だと思うんです。

[後編「メジャーな価値観によって成立している既存の世界の傍に、別の世界を並置する。」に続きます]
構成:二ッ屋絢子
取材・撮影・編集:後藤知佳(numabooks)
(2015年5月29日、FANCLUBにて)
[「アソシエーションデザイン」関連イベントのお知らせ]
林暁甫×寺井元一「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」
「混浴温泉世界」(別府)、「鳥取藝住祭」(鳥取)に加えて、直近では六本木アートナイト、同じく六本木での「リライトプロジェクト」など、地方と都心を横断してアートプロジェクトに関わってきた林曉甫さんをゲストに招き、地域アートプロジェクトについて考えるトークイベントを行います。
開催日:2016年4月29日(金・祝)15:00〜18:00(14:45受付開始)
出演:林曉甫(NPO法人inVisible)、寺井元一(MAD City/まちづクリエイティブ)
定員:30名 ※定員を超えた場合、ご予約の方を優先いたします。また、立ち見の場合がございます。
参加費:1500円(1ドリンク付き)
会場:FANCLUB(JR/新京成線松戸駅徒歩2分)
主催:株式会社まちづクリエイティブ
協力:DOTPLACE
★イベントの詳細・ご予約はこちらのURLから(ご予約は前日まで受付中)。


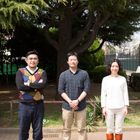











COMMENTSこの記事に対するコメント