大山エンリコイサム+寺井元一
「ストリート・アートと公共性
――表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで」
ストリートにおける表現活動とまちづくりは、これまで、そして今後どのように共生していくのか? 千葉県松戸駅の半径500メートルを「MAD City」と名付け、アーティストやクリエイターを誘致してまちづくりを行う「まちづクリエイティブ」の代表・寺井元一さんと、MAD City内のアトリエにかつて入居していた美術家であり、グラフィティ文化に関する論考集『アゲインスト・リテラシー』を2015年に上梓した大山エンリコイサムさんが対談を行いました。
●本記事は、2015年5月23日に本屋B&B(下北沢)にて開催されたイベント「ストリート・アートと公共性 表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで ――『アゲインスト・リテラシー グラフィティ文化論』刊行記念」を採録したものです。
●連載「アソシエーションデザイン つづく世界のつくり方」本編はこちら。
【以下からの続きです】
1/4:「グラフィティ文化は『匿名性』の一言で片付けられるものではない。」
2/4:「『やれない理由はそこにはない』というその様が、僕にとっての『ストリート』かもしれないですね。」
3/4:「公共空間は『みんなが納得することじゃないと実行できず、一人では使えない場所』になってきている。」
[4/4]
「循環」を前提としながら持続的な関係性
大山:まちづはアーティスト・イン・レジデンスもやっていますが、移動するアーティストたちの滞在を一時的にサポートするプラットフォームになっているわけですよね。プラットフォームを提供する側と、そこに一時的に寄り添い、何かを創作していく作家側の関係性というか、立場の棲み分けは、アーティスト・イン・レジデンスを持続するシステムとして捉えたときにどう機能しているのでしょうか。
寺井:僕にとっては、大山さんのようなアーティストがずっとMAD Cityにいてくれたらいいわけですよ。でも、そのアーティストが出ていくことが同じぐらい良いことになってくれればいいなと感じています。「移動」ということを前提にして、でも持続的に関われる関係性ができるといいですね。
大山:「移動」でもよいし、もっと言えば「循環」。きて、出て、また戻ってきて、また出てみたいなイメージです。移動を続けて、再訪しての繰り返しがいろいろなところで発生し、プラットフォーム側も、プラットフォーム同士でつながり、ネットワーク化できる状態が生まれるとよいですよね。

寺井:一方で、僕はどこか踏みとどまりたいという気持ちがあります。自分が街に行って従属するだけではなく、自分たちが主体になれるようにしたい、そうあるべきなんじゃないか、と思ったりする。「みんなができるわけでもない」という大山さんの発言につながると思うんですが、誰もがアーティストというわけでもないなかで、じゃあみんなどうしたらいいんだと、その疑問を掘り下げたくなりました。
そのときにひとつの可能性として模索したいのは、結局誰か一人が苦情やクレームを言うことによって何かが禁止になっていくことに対し、対抗できるような物語やコミュニティのようなものをつくれるかどうかという話です。それはMAD Cityのなかで取り組んでいるもののひとつで、地元コミュニティと接続することによって、もうひとつ新しい常識のようなものをつくろうと試行錯誤しています。
具体的には、江戸時代からその土地にいるような「地元」の方々が松戸にもいて、彼らは近所の土地も「政府に貸してやっている」という感覚があったりするんですね。なので、彼らは好き勝手に振る舞いますし、それがローカルルール化しているところもあるんですね。先住者としての正統性を持っているので、法的に保証されているかどうかはともかくとして、地域特有の常識や慣習に近い形で、一定の権限を持っている。その人たちは基本的に高齢者でこれから元気を失っていく、いきつつあるのですけれど、できれば彼らの特有性を活かしたり、引き継いで、カスタマイズするようなことができればいいなと思っていたりします。『アゲインスト・リテラシー』ではオーセンティシティというかたちで出てくるのですが、そういうものをどうコントロールするか、に近いかもしれません。
大山:「オーセンティシティ」は「真正性」と訳されますが、都市論の用語です。アメリカの社会学者シャロン・ズーキンが提唱していて(※シャロン・ズーキン『都市はなぜ魂を失ったか』講談社、2013年)、松戸で起こっていることにも当てはまります。もともとその土地の起源とされる伝統や文化、住民が築いてきた日常生活があったところに、外部から若者やアーティストが流入し、さらに後追いのミドルクラスやデベロッパーが介入して、だんだん土地の真正性が変化していくという現象をめぐる議論ですね。「融合的ジェントリフィケーション」という言葉もありますが、変化した新しい真正性がしばらく経つと古くなり、また別の力学によって新たな真正性に塗り替えられていくわけです。
おそらくそれは都市の問題だけでなく、文化一般に敷衍して言えることです。たとえば現代アートはそうした刷新の原動力によって進化してきた側面がある。80年代にグラフィティ文化の視覚言語がジャン=ミシェル・バスキアやキース・へリングのような新しいタイプのアーティストによって絵画の領域に導入されたとき、古い価値観からすればそれは許容しがたいことだったわけですが、今では彼らは巨匠の位置づけになりつつあります。世代が進むと「美術とは何か」ということが拡張されていくわけですね。

ヒップホップというもうひとつの強い記号
大山:同じことがグラフィティとストリート・アートの関係性についても言えます。最初期のストリート・アートはグラフィティ文化のインサイダーから亜流と思われていましたが、今ではむしろより大きな潮流になりつつあります。軋轢や批判を含みつつ、時が経つにつれて価値観が更新され、「本物性」の在り処が変わっていくという現象ですね。そういう意味で、『アゲインスト・リテラシー』が日本でのグラフィティ文化観を少しでも刷新できれば嬉しいです。
寺井:匿名性によって括弧に入れられてしまって、それでしか見られなかったものを括弧の外に引きずり出すというか、いろいろな見方がされるようにしていきたいということですか?
大山:匿名性の話につなげるなら、そういうことですね。また、ヒップホップというもうひとつの強い記号によるラベリングもあります。グラフィティ文化はヒップホップの一要素という考え方は必ずしも間違ってはいないのですが、それだけだと見落とされてしまうことが多いのもまた事実です。
グラフィティ文化がヒップホップの一要素だという括りは、1983年に公開されたチャーリー・エイハーン監督による映画『ワイルド・スタイル』にある程度まで起因しています。僕はチャーリーと何回か話をしていて、本人もそこはわかっているようです。ラップやDJ、ブレイクダンスは行為者が目の前にいるじゃないですか。グラフィティは目の前にいない。まさに匿名性の問題がここにあるわけですが、どういうエスニシティの人がやっているのか部外者は想像するほかなかった。そこで何となくヒップホップの延長線上で、アフリカ系アメリカ人やラティーノの人たちだろうと想像されてしまうことが多くて……そして『ワイルド・スタイル』以降は、そこがさらに強烈にラベリングされてしまった。

映画『ワイルド・スタイル』公式サイトより(スクリーンショット)
でも本当はそんなことなかったんですよ。もっと多人種だったし、音楽的にはパンクやメタルとも結びついていた。日本だと80年代がニューヨークのグラフィティ文化のオリジンだとか、『ワイルド・スタイル』は伝説のヒップホップ映画と言われていますが、実際はそのさらに前に70年代という重要な時代があるのが案外見過ごされている。70年代と80年代は、2000年代前半にグラフィティ文化に興味を抱いた僕の世代からすると、どちらもオールド・スクールの伝説的な時代という印象だったのですが、ニューヨークに住んでみて、そのふたつもまた異なる時代だったんだなと少しずつわかりました。
最初期のオリジネーターたちにとっては、まず69年から72年の3年間、それから73年から80年前後までの数年間、さらに80年以降というのは、すべて違う時代です。いわゆるヒップホップの一要素として表象される前のグラフィティ文化の時代があったし、それは日本で受容されてきたイメージとは異なるわけです。
寺井:おそらく日本の場合は、ヒップホップの4大要素(ラップ、DJ、ブレイクダンス、グラフィティ)みたいなものも含め、あるときにラベリングされたものをそのまま日本に輸入し、理解し、見えていない部分が多いまま、そこに乗っかってしまっているという意味でしょうか。
大山:日本だけではないですけどね。ある種のグラフィティ文化に対するステレオタイプなイメージが、とくに80年代に映画や写真集といったメディアの力で各国に伝わっていった。ヨーロッパや日本で『ワイルド・スタイル』を観てグラフィティを始めた人はいっぱいいます。先述したオランダのZEDZ(1971年生まれ)もそうです。それはやはり80年代以降の現象ですね。
でも、グラフィティ文化の前提となるさまざまな伏線がアメリカにはあったんです。それはトーク冒頭でも言ったように、ホーボーによる大陸横断鉄道の落書きとか、そうしたものですね。一見グラフィティ文化に直接結びついてはいないけど、文化史として俯瞰して見るとひとつの線になっている。逆に言うと、ヒップホップ的なグラフィティはあくまで80年代以降のステレオタイプに過ぎない。それ以前の風景が膨大にあるわけですよ。それを丁寧に辿っていくと、ヒップホップとか裏原文化に結びつくようなわかりやすいファッション的表象だけじゃ括れないものが見えてきます。『アゲインスト・リテラシー』ではそういうことを描きたかった。

「ゲーム」の枠組みのなかで「プレイ」して、「ゲーム」を書き換えていく
寺井:あと、まちづくりをやっている人間として興味が湧くのは、ヒスパニックや地下道のギャングの人たちやホーボーの人たちという特殊な人たちがいろいろとやっていたという「ゲーム」と「プレイ」の話ですね。
大山:「ゲーム」には外在的なルールがあって、たとえばスポーツです。サッカーだと手を使ってはいけないとか、あらかじめプレーヤーの外部にある共有されたルールに基づいて遊びますね。
「プレイ」は、たとえば子供がふたりで新しい遊び方を考えて、状況に応じて最初に決めた遊び方を変更したり、自発的に遊戯空間を産み出していくようなものと定義しています。子供が成長するにつれ、最初は落書きや真似っこなどの自発的な「プレイ」だったものが、小学生くらいになると体育の授業でサッカーをやったり、決まったルールで役割分担したり、「ゲーム」にシフトしていく。
寺井:大山さんもご存じの池田剛介さんと、別途でもアートとまちづくりに跨ったトークをしているんですけど、MAD Cityが行なっているまちづくりにおいてアートがまちや社会に何ができるのかを考えている。大山さんが触れている「プレイ」の概念も通じているところがあるのはないかと感じたのです。
まちづくりとアートの接点って、「参加型アート」と呼ばれる、地域アートプロジェクトにみんな参加しなきゃいけないというスタイルで、その“参加しないといけない”ということも含め、池田さんは違和感みたいなものを覚えているようです。なので、遊びそのものではなく、参加する/しないということでもないところ、もうひとつ街をつくろうというところに「プレイ」との接点があるのかなと考えていて、そのことについて聞きたいのですが、大山さんはそのあたりどう評価しているのですか。

大山:表現の世界だと、「ゲーム」の枠組みそのものを壊して新しいものを生み出していくことが必要で、単純に決められた規則に沿ってやっていれば評価されるわけではない。そういうのはせいぜい受験のときくらいじゃないですか。本質的には「プレイ」の創造力で枠組みを新たに産出していくことが必要になると思います。
ただ、プレイもゲームもあくまでモデルであり、現実には両者は融合していますよね。どちらの要素も混ざっている場合がほとんどだと思いますし、むしろだからこそ、既存のルールを読み替えていくということが起こり得る。アートや文化というのはそういうものだと思っています。
グラフィティ文化の話でいうと、ある程度それが様式化されて以降は、さまざまなルールができて制度化していく。スローアップのうえにタグをかいてはいけないとか、決まりごとができちゃうんですね。うっとうしい気もするけど、同時にそのなかで競争関係があるから新しいスタイルが生まれ、発展していく。ゲームとプレイのどちらがよいかは一概には言えないですよね。
寺井:しばらく前にネットで話題になっていた小学生がつくったカードゲームがあって[★4]、その小学生が一応ルールをつくっているのだけど、その説明がどういう風にでも読めるようで、やる人によって解釈が違うからゲーム自体が変わるという、その面白さが話題になっていたんですけれど。
★4│小学生がつくったカードゲーム「光ネッサンス」:
http://gamemarket.jp/game/%E5%85%89%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9/
http://togetter.com/li/820349
もしかしたら僕がやりたいまちづくり的なことで言うと、仕組みはわからないのだけど、その外在化しているルールを内在化しうるものだと捉え直すことなのかもしれません。法律の解釈も本来はそういうものだと思いますし。その解釈を誰ができるのかは簡単な話ではないですが、自分たちのローカルな生活のルールをもう一度考えてもいいのではないか、ゲーム化することで考え得るのではないかと思いました。そのカードゲームがヒントになりうるように、もしかしたらアーティストがやっていることがひとつのヒントになっているのかもしれないし、もしそうだったらすごく面白いですよね。
大山:なるほど。それはある意味で解釈のアドリブの問題ですよね。作曲家の芥川也寸志さんは著書で「100%フリーのアドリブは存在しない」とかいています。つまり、台本で決められたレールや枠組みがあるからこそ、そこからはみ出るアドリブが可能になる。これは表現の自由の問題とつながってくるけど、自由の感覚は、なにか枠組みを踏み外しているからこそ立ち上がるとも言えるのですね。

表現の自由というのは「何でもやっていいですよ」という話ではなくて、絵をかくにも歴史的に積み重ねられた文脈があって、それを知っているからこそ、それを解体して壊すこともできる。逆に言えば、何もないまっさらな状態で、破壊すること、自由を感覚することは困難になってしまう。カードゲームの例で言えば、手がかりになるルールがまず与えられているからこそ、自由で多様な解釈が引き出される。プレイとゲームの関係もそういうものなのかなと。
寺井:勇気をもらえますね。「街のなかにある当然とされているものを、“書き換えられるもの”かもしれないと仮定してもう一度見てみましょう」というゲームになるだけで、もしかしたら変わっていくものなのかもしれないですね。
僕はまちづくりって普通、行政がやっているイメージだけど、勝手に僕が一応なんとなく小さなエリアのなかで住民を増やすことをできているというのはある意味、変なまちづくりをやる実験場をもらっているような感じがあるので、そこでいろいろなことを試したいなと考えてます。
大山:外部からきた人の方がプレイしやすいのかもしれないですね。地元のしがらみもなく、客観的に観察することもできる。ほかでやっていたことのリソースや経験が活かせる部分もある。そこにある既存のゲームのロジックとは別の原理をもちこむ。寺井さんが松戸でやっていることは、そういうことではないでしょうか。
寺井:そうですね。今後、その成果がレポートできるようにしたいなと思いました。本日はありがとうございました。

[大山エンリコイサム+寺井元一:ストリート・アートと公共性 ―表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで 了]
構成:吉崎香央里、後藤知佳(numabooks)
取材・撮影・編集:後藤知佳(numabooks)
(2015年5月23日、本屋B&Bにて)
[「アソシエーションデザイン」関連イベントのお知らせ]
林暁甫×寺井元一「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」
「混浴温泉世界」(別府)、「鳥取藝住祭」(鳥取)に加えて、直近では六本木アートナイト、同じく六本木での「リライトプロジェクト」など、地方と都心を横断してアートプロジェクトに関わってきた林曉甫さんをゲストに招き、地域アートプロジェクトについて考えるトークイベントを行います。
開催日:2016年4月29日(金・祝)15:00〜18:00(14:45受付開始)
出演:林曉甫(NPO法人inVisible)、寺井元一(MAD City/まちづクリエイティブ)
定員:30名 ※定員を超えた場合、ご予約の方を優先いたします。また、立ち見の場合がございます。
参加費:1500円(1ドリンク付き)
会場:FANCLUB(JR/新京成線松戸駅徒歩2分)
主催:株式会社まちづクリエイティブ
協力:DOTPLACE
★イベントの詳細・ご予約はこちらのURLから(ご予約は前日まで受付中)。


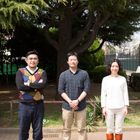











COMMENTSこの記事に対するコメント