大山エンリコイサム+寺井元一
「ストリート・アートと公共性
――表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで」
ストリートにおける表現活動とまちづくりは、これまで、そして今後どのように共生していくのか? 千葉県松戸駅の半径500メートルを「MAD City」と名付け、アーティストやクリエイターを誘致してまちづくりを行う「まちづクリエイティブ」の代表・寺井元一さんと、MAD City内のアトリエにかつて入居していた美術家であり、グラフィティ文化に関する論考集『アゲインスト・リテラシー』を2015年に上梓した大山エンリコイサムさんが対談を行いました。
●本記事は、2015年5月23日に本屋B&B(下北沢)にて開催されたイベント「ストリート・アートと公共性 表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで ――『アゲインスト・リテラシー グラフィティ文化論』刊行記念」を採録したものです。
●連載「アソシエーションデザイン つづく世界のつくり方」本編はこちら。
【以下からの続きです】
1/4:「グラフィティ文化は『匿名性』の一言で片付けられるものではない。」
[2/4]
合法であることによって人がアクセスできる
寺井:いったん、質疑応答に入りたいと思います。
質問者1:寺井さんが先ほど話されていたリーガルウォールの活動の傍らには、当然イリーガル(違法)な部分があったわけですよね。リーガル(合法)には関与するけど、イリーガルは放置する、あるいは、関心を持たなかったということだったんですか。そこにはどのように働きかけていたのでしょうか。
寺井:僕としてはすでに一度終わっている活動なので、当時どう思っていたかという説明になりますが……イリーガルな活動、そしてその当事者に個人的興味はありつつも、法人としての活動においてはそこに対する価値判断はしない、コンプライアンスとして自分たちはイリーガルなことはしない、というのがそのときの僕のスタンスです。今日の話につながるかもしれないですが、イリーガルなものや、匿名性があって人から見られないものにも、価値が眠っているのではないかと考えていたんです。その、価値が見えなかったり眠っているような、ブラックボックスとしてのイリーガルな活動のなかに、リーガルのなかで成立するものとか、他の人が見たときに価値を感じられるものがあるはずで、それを引っ張り出してきたい、というのがモットーでした。なのでグラフィティの方と関わるときに、彼らが過去の背景に持っている法的な合法/非合法とかは、僕の価値判断から積極的に切り離していた。今と未来に僕らが彼らに関わるとき、合法的な枠組みで一緒にできるかということに注力していたんです。そこに意味や価値がありそうなものであれば、それがいつだって人に見られるようにしていくための装置として、リーガルであることって必要だろうなと思っていました。僕は別にイリーガルに関わることに一周回った当事者的な特別さを感じるとか、逆にリーガルでありたかったわけでもなくて、「リーガルであることによってアクセスできる」ということ自体に当時価値を感じていました。

当然、いろいろとかなり誤解して理解されたところがあって、「落書きをもっと消してください」みたいなことも言われていましたが、別に落書きが嫌だったわけではなく、落書きが存在できるリーガルな場所をつくるのが僕にとってのベストだったんです。「イリーガルで犯罪だと見なされるものをどう取り締まるか」という問題には、僕は関わらないようにしていました。これを「無責任だ」と言う方もいたはずですが、僕はそこを引き受けるつもりはなく、それは警察がやることで、僕には別の役割があるという割り切りのなかでやっていました。
大山:寺井さんにとって法律はどちらかというと「素材」で、自分のやりたいことのためにそれをどう利用するか考えていたんですね。逆に言えば、そこに価値判断はないわけですか。
寺井:価値判断はなかったですね。法律というものは、社会環境のなかで創られる結果だと思っていて、善悪とは別物だと思っています。もちろん非合法なものは理由があって法的にそうなったわけで、僕も罰されることに同意できることが大半なわけですが、それも結果でしかないと思うんです。でも、一般的には「価値判断が入っていないわけがない」とは思われていたでしょうし、それに苦しんだ時期もありました。結果として、「価値判断をしていないと許されないのではないか」とか、そのようなせめぎ合いのなかで、自分の居場所がなくなっていくことをどんどん実感していったというのはあるかもしれないですね。僕にとっては単なる道具だったはずのものが、道具では許されなくなったのでしょうね。
「イリーガル=本物」という現場主義から脱出せずに新しいものは生まれない
大山:グラフィティの表現力や可能性をより広くアクセスできるようにするという話だったと思うのですが、合法的な状態にするとその魅力が変容してしまう、場合によっては失われてしまう可能性はなかったのか。これは僕もよく言われますし、寺井さんも考えていると思うのですが、ある意味正しい指摘ですよね。ただ「イリーガル=本物」という現場至上主義はひとつの原理主義ですから、それはそれで視野が狭く、そこから外れるものは検証なしに問答無用で「ダメ」となってしまう。でも本当にそれでいいのか。先述した匿名性の問題と同じで、これでは一元的なラベリングですし、「犯罪だからアートじゃない」というアンチ・グラフィティ主義の反転です。本来イリーガルであることは逸脱性があるものだったのに、それが原理主義になることで制度性を帯びてしまうのはある種の矛盾ですね。
要するに、合法/非合法という二項対立で考えること自体がもう古いんです。その図式からこそ逸脱しないと新しいものは生まれないと僕は考えているので、手さぐりであれ、そういうことをやるべきだと思います。

寺井:挟まれる、かどうかで言えばずっと挟まれる場所にいたんです。たとえば、リーガルウォールとして描かれたものの上に、イリーガルな人たちに落書きをされる、というのはゼロではなかったわけですよ。それに対して、短期的には面倒くさいとか、それどうするの、みたいなことも言われるんですが、僕にとってはそれほど嫌なことではなかったんです。自然なことというか、「健全だな」という感覚がありました。そういう意味では……イリーガルと呼ばれているものにも、僕は健全性を感じました。
この本にも出てくると思うのですが、ゴーイング・オーヴァー(ライター同士が互いのグラフィティを上書きし合う応酬戦)のような有機的なつながりによって、何かが落ち着いていくことってあるじゃないですか。日本のグラフィティの場合、最後に暴力が出てくることがあるので、それが健全かと言われれば違うのですが、ある種の相互作用のなかで何かが生まれていっていること自体は価値だと思います。僕が伝えたかった「グラフィティが持っていた魅力や可能性」というのはそういう点にあった気がしますね。
大山:その相互作用というのは、違法かどうかは関係なくて、競争性があるか否かではないでしょうか。つまり、上書き行為の応酬のなかで切磋琢磨しながら、新しいスタイルや表現が生まれてくるということが魅力なわけです。そうした競争性から生まれてくる表現の進化はグラフィティ文化に限らず、アート全般について言えます。アーティストはつねにコンペティションしているわけですから。そう考えると、アートもグラフィティも、合法も違法も関係ないんですね。表現者として力のある作品を生み出せるか、ただそれだけです。
寺井:公共空間や街という自分たちの実践の場において、合法/非合法だと簡単に是非の判断をして終わらせることもできるけれど、そうでなく、本質的に何に自分の価値を委ね掘り下げていくのかを、この後話せたらいいですね。
「やれない理由はない」というストリートの原始的な価値判断

質問者2:ストリート的なものをまちづくりやアートに持ちこんできたお二人は、ストリートのエッセンスやリテラシーを利用しているのかなと感じたのですが、お二人にとって「ストリート」というのはどういうものなのでしょうか。
大山:「ストリート」というのは大きな言葉で、グラフィティ文化の視覚言語をアートに取りこんでいると言った方が僕の場合は正確です。「利用」と言うより不可避的に影響を受けてしまったので、自然に、でも抜き差しがたく自分に埋めこまれています。
その影響というのは、ヴィジュアル・ランゲージとしての強度みたいなものですね。グラフィティ文化あるいはストリート・アートは、これまで日本では主にふたつのパターンで受容されてきました。ひとつはバンクシーのようなアクティヴィズムのタイプで、政治的・社会的メッセージがあり、カルチュラル・スタディーズの枠組みで理解されやすいパターン。もうひとつはキース・へリングのようなポップ・アートのタイプで、コマーシャルな文脈や原宿なんかのファッションおよびグラフィック・カルチャーと親和性の高いパターン。グラフィティ文化に対する僕の関心はどちらとも違っていて、抽象表現主義やメキシコ壁画運動といった近代美術が産み出した視覚表現の系譜に引き寄せて考えたいのです。

少し前提を話すと、そもそもグラフィティ文化の土台を築いた70年代ニューヨークのライターたちは当時10代前半のキッズだった。そんな少年少女たちが、左翼の理論家が説明するような反権力の闘争に真剣に取り組んでいたわけではないのは明らかで。そうしたアクティヴィズム的なラベリングは、グラフィティ文化を意味づけしようとする大人たちによって事後的に与えられたものに過ぎません。実際のキッズたちは、新しく考案したタグ・ネーム(グラフィティ用の名前)に想像されたアルター・エゴ(もうひとつの自我)を仮託して膨らませ、爆発させる。そして、そこから生まれる独自のスタイルを競い合わせるということに夢中になっていたわけで、それはアドレナリンが分泌するような興奮感覚をともなう視覚言語の強度の問題なんです。
でも結果的にそのエネルギーが膨らみすぎて、地下鉄という公共の媒体にまで拡張し、都市全体に流れていったため、即座にそれは社会問題になり、メディアで吹聴され、ヴァンダリズム(器物破損)と呼ばれてしまった。「グラフィティ文化 VS オーソリティ」という構図が形成される。その枠組みがあればインサイダーでなくてもグラフィティ文化について語りやすいし、問題として位置づけやすい。同時にライターたち自身も成長するにつれ、自分たちは警察や市民社会に牙をむくアウトローであるという物語を内面化し、アイデンティファイしていく……先述したイリーガル=本物という原理主義の萌芽はここにありますが、文化の胎動期にグラフィティを始めたキッズたちが本当は何に取り憑かれていたのかというと、そんな社会的なことではなくて、もっと純粋な想像力の爆発みたいなことだったと思うんです。それは抵抗文化の物語に意味づけされる以前の情動で、それこそがグラフィティ文化の素晴らしいヴィジュアル・ランゲージを産み出した本当のエッセンスだと考えています。
アーティストとして僕がやっていることは、このグラフィティ文化の視覚言語からもっとも強度のある描線を抽出し、反復することで「クイック・ターン・ストラクチャー」というミニマルなモチーフを構成することです。それは美術史の文脈でいうと、やはり抽象的な造形言語を押し進めた抽象表現主義などの問題につながっていくと思っています。

Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #88, 2013-2014
Artwork © Enrico Isamu Oyama
Photo © Atelier Mole

Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #117, 2015
Artwork © Enrico Isamu Oyama
Photo © Norihiro Ueno
寺井:勝手に大山さんの話に付け加えると、『アゲインスト・リテラシー』は評論だし、難しいことがいっぱい書いてあるのかなと思っていたけど、最後の最後で急にアツい本になっていて、「ここまで書いていて語りえない何かが自分のなかでの存在感を出すのだ」という風に書かれていて、それが今の話とすごくつながりました。
一方、僕にとっての「ストリート」なのですが、立ち位置の違いもあると思いますが、大山さんとは不思議なぐらいに違います。僕がKOMPOSITIONでやっていたときに、「ストリート」とは何かと社内で言おうとなりまして……というのも、グラフィティ寄りのリーガルウォールをやって、その次にストリートバスケットの大会をやるようになって、その後もBMXとかセパタクローとかに関わるようになるのですが、とにかく方向性がよくわからないわけですよ。KOMPOSITIONは最初はボランティアを集めて公園の壁の落書きを消していたので清掃団体・環境団体だと思われていて、壁に絵を描くようになったらアート団体だと思われるようになり、バスケとかをやるようになるとスポーツの団体なのかと問われ、それを利用して戦略的にやってきてもいたのですが、社会的にはどんどんわからない団体になっていく。そこで根本では何を考えているのかということをどこかで表明するしかない、という議論があって……表明まで至らずに活動を停止したんですが。「ストリート」というのが教科書的にどう定義されているのは僕にはわかりません。ただ、僕にとってはすごく、自由とか生きる希望につながる概念です。
大山:補足すると、寺井さんはもともと政治の畑にいた人で、ストリートに関わる活動をする前に政治家の秘書をやっていた。このコンテクストは重要です。「政治で街を変えられないから、ストリートから街を変える」と昔言っていたのを覚えていますよ。
寺井:もとは政治家の秘書から選挙分析の研究者になったから、自分の分析をしたら選挙に受からないということがわかって、「自分に投票してくれる人を増やすしかない」とアクティビストになり、アクティビストとしてやっている間にストリートに触れて、そのうちにストリートと呼ばれている人たちのような生き方は良いなと感じましたね。
リーガルウォールだけやっていたときにはそんな風に感じられなくて……というより、そこにあったはずなんですが、知覚できなかったなと思っていて。僕がそれを自分なりに掴めたのは実はストリートバスケットボールのときでした。ふたつの視点があったから「ストリートってこういうものなんだろうな」と思えたというか。

ストリートバスケの世界でいうと、あのスポーツは何人ででもできるんですよ。結構これがすごくて。3on3というのが一番有名なんですが、1on1、2on1、4on4でもいいんです。2人でも10人でもできるスポーツってあまりないですよね。役所とストリートバスケットの話をしていると、「5対5じゃないとできない」とか、「予約しないといけない」とか、「上手いヤツと下手なヤツが戦ったらどうなるのか」とか、いろいろな問題が出てくるんですが、ストリートバスケの感覚でいうと、関係ないんですよ。下手なヤツも今始めればいいじゃない、という話で。上手い/下手というのはストリートバスケットをやっている人たちのなかでは感覚として薄い。誰が始めてもいいし、下手くそでも、やるってだけで「お前は良い!」みたいな雰囲気になるんです。“原始的な価値判断”をしてくれるわけですね。
ストリートの人たちが持っている価値観が、僕の本質的な問題意識に近かったんでしょうね。誰だって、いつだって始めていい。下手とかうまいとか関係ない、やりたいことやればいい、やめたいときにやめればいい、場所も限定しない、バスケができない場所だとしてもそこをバスケのコートにすればいいじゃない、という考え方ですね。
今自分がいることをすごく肯定してくれて、そこから何かを始めることやできない理由をすべて払拭してくれるのが、僕にとってはストリートの概念ですね。ヒップホップの4大要素というものをやってきた人たちがいて、今はそのイメージが固定化されているわけですけど、でも根本的には自分のやり場がない人たちがおそらく多かったであろう黒人やスラム街にいた人間が、ストリートというものに自分の生きる道を見出した理由が、なんとなくですけど、勝手にわかるような気はしています。
僕の初期衝動として、そういうものに支えられている街をつくりたい、そういうところで生きていたいという思いが、僕の価値判断につながっている気はしますね。限りなく「やれない理由はそこにはない」というその様(さま)が、僕にとっての「ストリート」かもしれないですね。
接続できないもの同士をつなげたいとき、ストリートにヒントがある
質問者3:お二人は、ストリートの何が有効だと考えているのでしょうか。
大山:ひとつには「アプロプリエーション」とか「ブリコラージュ」という考えがありますね。一番わかりやすいのはDJのスクラッチングかな。レコードは本来プレーヤーで再生して音楽を聴くものだけど、擦ると音が出るから楽器にしてしまうという発想です。グラフィティ・ライターも、地下鉄の車体をキャンヴァスに見立てて名前をかき、街中に流通させた。あるものを本来とは異なる仕方で活用することで、ゲリラ的に自分たちのものに転用するというスタイルは、ストリートのエッセンスのひとつと言ってもよい。ブリコラージュはもともと文化人類学の用語で、未開社会の創作技法のことですが、それは現代社会にもあてはまる部分があります。
寺井:僕個人が感じる「ストリート」から流用できる一番の点というのは、MAD Cityだったら、ロゴを付け直す、名前を与え直すという行為でしょうか。それはさっき大山さんが言っていたアルター・エゴの話でもあるわけです。
ストリートにおける生き様とかやり方というもののなかには、実はそれぞれの人が自分のなかに取り入れることができる生き方の知恵みたいなものが結構あるのではないかなという気持ちはあって、ストリートでみんなが実際にやってきたことをうまく使うことによって、社会との関わり方を少し変えることができるのかもしれません。
たとえば政治家というとすごく狭い人種ですが、「ストリートの政治家」という言い方を使うと、いかにもその辺を歩いているおじさんも政治家に見えそうじゃないですか。自分には接続できないものをつなげていったりとか、巻きこんでいったりするためのツールとして、ストリートという言葉だったり、そこで起きている様式・やり方みたいなものを共有していけたら、もしかしたら社会の権威化、オーソライズの在り方を流動化して、新しい可能性が生み出せる気がします……。
ただ、外から入って来れないために誰も語れない点がストリートの難しいところとして出てきているように、「それは本物じゃないぞ」みたいなことをつい言われてしまうので、誰もそれを体系化できないのでしょうね。無理に体系化しなくてもいいという向きもありますが、いずれにせよこれまで生きるための糧として利用し、加工できる人が本当に少なかったのだろうなと思っています。
そういう意味では今回、『アゲインスト・リテラシー』を読んで、この本が出版されたことは重要なのかもしれないと思ったりもしますね。
[3/4「公共空間は『みんなが納得することじゃないと実行できず、一人では使えない場所』になってきている。」に続きます]
構成:吉崎香央里、後藤知佳(numabooks)
取材・撮影・編集:後藤知佳(numabooks)
(2015年5月23日、本屋B&Bにて)
[「アソシエーションデザイン」関連イベントのお知らせ]
林暁甫×寺井元一「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」
「混浴温泉世界」(別府)、「鳥取藝住祭」(鳥取)に加えて、直近では六本木アートナイト、同じく六本木での「リライトプロジェクト」など、地方と都心を横断してアートプロジェクトに関わってきた林曉甫さんをゲストに招き、地域アートプロジェクトについて考えるトークイベントを行います。
開催日:2016年4月29日(金・祝)15:00〜18:00(14:45受付開始)
出演:林曉甫(NPO法人inVisible)、寺井元一(MAD City/まちづクリエイティブ)
定員:30名 ※定員を超えた場合、ご予約の方を優先いたします。また、立ち見の場合がございます。
参加費:1500円(1ドリンク付き)
会場:FANCLUB(JR/新京成線松戸駅徒歩2分)
主催:株式会社まちづクリエイティブ
協力:DOTPLACE
★イベントの詳細・ご予約はこちらのURLから(ご予約は前日まで受付中)。


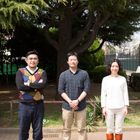











COMMENTSこの記事に対するコメント