
フリーライターの鷹野凌です。ブログ「見て歩く者」では毎週月曜日に、DOTPLACEでは月末に、「出版業界関連の気になるニュースまとめ」を配信しています。気になったニュースをピックアップし、理由、経緯、感想、ツッコミ、応援などのコメントを付けています。私のピックアップなので、著しく電子出版関連に偏っています。
2015年2月3日
2015年2月11日 2本まとめてピックアップ。どちらもすでにNHKニュースからは消えているため、Internet ArchiveへのURLを張っておきます。TPPは秘密交渉なのに、なぜかときどき観測気球的に情報がリークされます。これまでは日経新聞が多かったのですが、今回はNHKです。この報道を受け、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラムが「TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ」をしています。知財に関しては秘密交渉ではなく、きちっと情報公開した上で交渉して欲しいという呼びかけです。
2015年2月6日 先月のまとめで「comico」アプリが800万ダウンロード突破という記事をピックアップしましたが、こちらはいきなり1000万ダウンロードです。無料で読める「LINE マンガ連載」のリリースが昨年8月で、グラフを見る限りその頃には既に800万ダウンロード到達していたようです。ただ、累計売り上げ49億円を1000万で割ると、1人あたり490円。「LINEマンガ」が始まったのは2013年4月なので、2年弱の数字として考えると、ダウンロード数のわりにアクティブ率が……という気がします。

LINE Corporationのリリースページより(スクリーンショット)
2015年2月15日 「ネットに親しんでいるイメージがある若年層のネット利用が少ないのは意外だ」と驚いている協会担当者のコメントが紹介されていますが、「クレジットカード」と各所から盛大にツッコミが入っていた記事。ところが同じく共同通信からの配信である日経の記事には、日本書籍出版協会の「10~20代はクレジットカードを持っていない人も多く、ネット上で決済ができないため通販を利用しづらい」というコメントも紹介されています。ネット通販で現金決済するには代金引換しかないので、なかなか難しいんですよね。
2015年2月17日 アムタスの「めちゃコミック」は、2014年3月期に売上100億円を突破しており、電子コミック関連で数字を公開している企業の中ではトップクラスです。そこがライトノベル配信にも手を伸ばすのは当然のことだとは思うのですが、少し興味深いのが「講談社・小学館の」という点。ライトノベルはKADOKAWAが強いのですが、今回のリリースには名前が出ていません。閲覧環境であるセルシスの「BS Reader for Browser」が、「XMDF形式に対応した」というリリース(PDF)が出ている点も興味深いです。これだけEPUBが普及してきた中で、なぜいまXMDFなのか。

「めちゃコミック」より(スクリーンショット)
2015年2月21日 恐らく警察発表そのままだと思うのですが、動機を「女子中学生と大人の男性との恋愛を題材にした電子書籍」を読んだのがきっかけだと供述しているそうです。こういう発表で「電子書籍」が出てきたのは、恐らく初めてではないでしょうか。どの作品なのかは不明ですが、話の中身は基本的に紙でも電子でも同じはずなので、わざわざ「電子書籍」と発表することには何か意図を感じます。そういえば一時期、LINEが叩かれる対象になっていましたね。
2015年2月20日 興味深い数字が公表されました。利用率の高い店舗では、対象誌を購入する10人に1人が利用しているとのこと。正直、利用率はまだまだこれから、といったところです。最初の登録さえ済ませておけば、店舗では購入時にTカードを提示するだけで良いという簡便さなので、最初の登録(Yahoo! JAPAN IDの作成と、BookLive!アカウントの作成と、その2つの連携)にボトルネックがあるのか、まだ認知されていないのか。
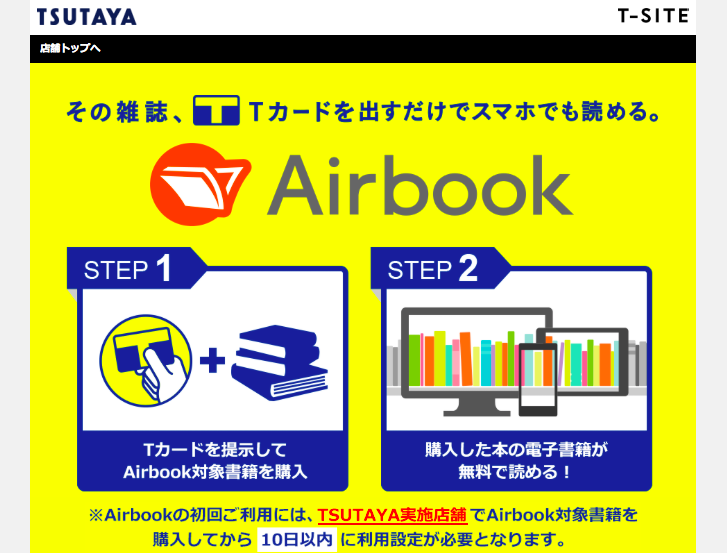
「TSUTAYA Airbookサービス」のページより(スクリーンショット)
2015年2月22日 他メディアでも報じられていますが、より詳細なこの記事をピックアップ。藤井太洋氏は2012年にSF小説『Gene Mapper』をセルフパブリッシングで出版、注目を集め才能を見いだされ、商業デビューを果たした作家です。その2作目『オービタル・クラウド』が、日本SF大賞を受賞。もう、なんというか、凄いの一言です。おめでとうございます。
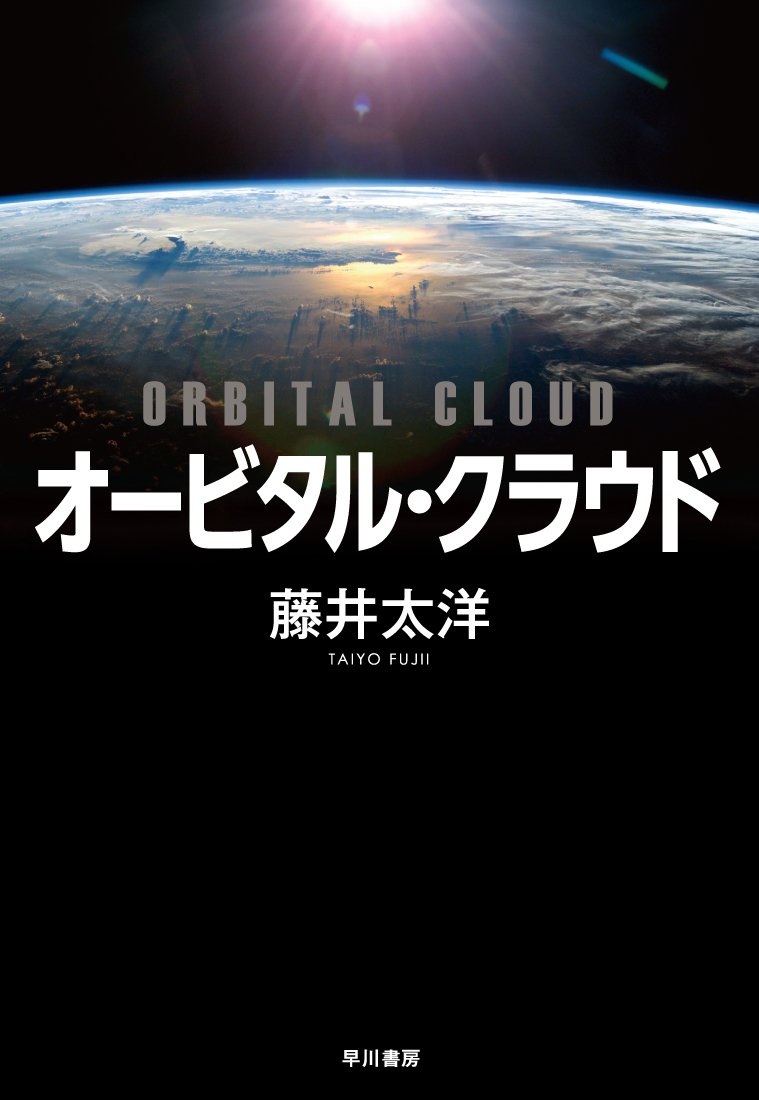
藤井大洋『オービタル・クラウド』
2015年2月23日
広がるか電子図書館 24時間貸し出し、自動「返却」 新刊少なく、著作権料が壁 電子図書館の現状についての記事。利用者のメリットは「無料」「24時間貸出」「自動返却」といろいろ挙げられますが、ネックはラインナップ不足。記事には話題のベストセラーや新刊本が少ないとありますが、むしろ過去に紙で出版された膨大な本がまだデジタル化されていない点の方が、図書館の果たす役割を考えると大きな問題のように思います。また、「同時に複数の人が借りられないのは、デジタルのメリットを損ねている」といった趣旨の反響が意外と多いのですが、無尽蔵に借りられるようになっていたら著者や出版社が干上がってしまう、という点も考慮して欲しいなと。
2015年2月25日 誰でもイラストやマンガが投稿できる場としては、以前から「pixiv」「TINAMI」「ニコニコ静画」などがありました。2013年10月に「comico」が、2014年3月に「マンガボックスインディーズ」が、同12月には「少年ジャンプルーキー」と、マンガに特化したCGM(Consumer Generated Media)が次々誕生しています。そしてついにLINEも参入です。真っ赤な海が見えますね。

「LINEマンガ インディーズ」より(スクリーンショット)
2月もいろいろ興味深い動きがありました。さて3月はどんなことが起こるでしょうか。
ではまた来月(=゚ω゚)ノ
[今月の出版業界気になるニュースまとめ:第3回 了]






COMMENTSこの記事に対するコメント