2013年12月、朝日出版社のアイデアインクより出版された内沼晋太郎(numabooks/DOTPLACE編集長)による著書『本の逆襲』。その発売当日に、内沼の活動を古くからよく知るお二人(編集者/文筆家の仲俣暁生さん、月曜社取締役の小林浩さん)と著者との間で交わされた鼎談の模様をお送りします。無限に拡張していく「本」の概念。『本の逆襲』を起点に、三者それぞれの視点から、“逆襲”はいかにして可能かを探っていきます。
★2013年12月11日、本屋B&B(東京・下北沢)で行われた、内沼晋太郎『本の逆襲』(朝日出版社)刊行記念イベントのレポートです。
【以下からの続きです】
イベントレポート「逆襲する本のために」1/5
イベントレポート「逆襲する本のために」2/5
イベントレポート「逆襲する本のために」3/5
イベントレポート「逆襲する本のために」4/5
「もう少しこの本にお金を使いたい」人たちのニーズを掴む
内沼:やっぱり僕は、バリエーションにはまだたくさんの可能性があると思います。
本って同じ本を2冊買うことってまずないじゃないですか。例えばビールだったら、サッポロが好きな人は、サッポロのビールに何十万も何百万も使っているかもしれないわけですよね、一生の間に。だけど本はそういう買い方ができない。「この本が俺の一生を変えた」という人も「クソみたいな本だったから、今すぐ捨てたい」という人も同じ値段を払っているし、「この本、すごく気に入ったから5冊買います」ということもないわけです。
無料のコンテンツがあふれる時代に、お金を払うということの意味も代わってきています。クラウドファンディングがいい例ですが、お金を払うことで応援や感謝の気持ちを表すという価値観が少しずつ浸透してきている。だから「これは僕にとって素晴らしい本だから、2万円払いたい」という人もいれば「どんな内容の本かまだわからないから、とりあえず200円で買いたい」という人もいる、と考えるほうが、これからの時代に即しているのではないかと思うわけです。それが、バリエーションを付けるということです。
紙の『本の逆襲』は987円ですが、今日このトークイベントに参加するためには1,500円+ワンドリンクで合計2,000円かかる。ここに来てくださっているお客さんのうち紙の本を買ってくださっている方は、987円+2,000円の本を買ってくれている人なんですよね。だからこの本には少なくとも「987円バージョン」と「2,987円バージョン」がある。
小林:デラックスエディションだ。
内沼:そう思うんです。それと、実は今回、この本の表紙のグラフィックが入ったトートバッグやステッカーといったグッズも作ったりしているんです。この本をいくら気に入ってくれた人にも、同じものの2冊目を売ることはできないけれど、「すごく気に入ったから、もう少しこの本にお金を使いたいよ」という人たちに「よかったらグッズを買ってください」「イベントに来てください」と言うことができる。例えばそういうことだと思うんですよね。もちろん、どういうバリエーションをつくるべきかは、本によって違う。
仲俣:よくあるのは、「電子書籍を買った後で紙の本を買っちゃう」っていうパターンですよね。「文庫を買った後でハードカバーの親本を買う」とか。同じ本を2冊はいらないけど、ハードが違ったりエディションが違えば、好きな本なら買うことがありますよね。
それに、何度も読むとコンテンツ自体の意味も変わってくるのが本だから、実は一人の人の中でも何度も楽しめる。音楽だったらもう少し「過去の思い出をもう一度」的な楽しみ方の需要に寄っているけれど、本は全然違うじゃないですか。覚えていることが書いていなかったり、覚えていないことが書いてあったり……その本が持っている多様性とか多面性が、今はあまりマネタイズできていない。
それと、大体の人は、本というのは「たくさん生産されていて、いつでも買えるもの」なんだと思っている。「見つけた瞬間に買わなかったら二度と買えなくなる」ということを知っているのは、業界の人だけなんです。
小林:月曜社では森山大道さんの限定版の写真集を出すことが過去に幾度かあったんですが、そういう本は古書業界の人や写真関係のプロフェッショナルな人たちの目に留まるのはものすごく早いんだけれど、一般への訴求力がどれだけあるかというといささか疑問があります。せっかく作ったのに、写真を始めたての学生さんや「森山さんの写真、面白いな」と思っている人たちの目につく頃にはもう在庫がない、という感じになってしまいがちなんですよね。
仲俣:例えば初刷が700部の本というのは「700部しか刷れないマーケット」なのかもしれないけど、「700人しか買えない本」でもあるわけですよね。だから、ビートルズのホワイトアルバムみたいに通し数字を付けて、著者がキリ番を所有する、みたいなことができるかもしれない。
内沼:『下北沢について』もそうですよ。これは、初刷だけ1から500までリミテッドで番号を入れていて、二刷からは入れないと決めているんです。そうすると、「やっぱり初刷が欲しい!」ってなりますしね。
仲俣:言い方を変えれば、内沼さんの言っていることは「出版界は儲け損なっているんじゃないですか」っていうことだと思うんです(笑)。
小林:その辺りに関しては、まったく反論の余地がないですね。この業界は本当に隙だらけで、いくらでもニッチなところがあるわけですよ。それなのに「ビジネスになるかわからない」とみんな思っている。そこで踏み留まっちゃうと、結局「必要ない」ということになってしまう。
だからこそ、そこに一歩を踏み出す――ひょっとしたら、やる前に「俺ってバカなんじゃないの」とか思うかもしれないけど、「バカでもいい」という潔さが必要だと思うんですよね。
どんな出版社も、新しい出会いを求めている
仲俣:内沼さんは色々なクライアントと仕事をされていますけど、紙で本を出している出版社から「もっと本を売るためにはどうしたらいいか」といった相談を受けることもあるんですか。
内沼:ありますね、たまに。でも、やっぱりそれは少し特殊な本の場合が多いです。「今回は特殊な売り方をしてみたいんだけど、内沼さんだったらこの本で何ができると思いますか」という感じで。その本だけにしか適用できない個別のアイデアを考えるのは楽しいし、そういう相談があるならもっと乗りたいです。仮に「予算がありません」という場合でも、面白くなりそうな話ならお受けしています。そこでいままでにない売り方で成功したときに、どこかで「内沼が考えた」ということだけは言うようにしてもらえれば(笑)、それがきっかけでまた仕事も増えるでしょうしね。
仲俣:出版社は今まで、印刷屋やデザイナー、写真家、イラストレーター、そしてもちろん著者という風に、外部の専門領域を持った人たちと一緒に仕事をしてきた。ということはつまり、オープンシステムなんですよね、出版って。自社の中だけでできることは限られている。
それなのに、プログラマーやマーケター、そして内沼さんのようなブック・コーディネイターとか、そういった新しいパートナーと付き合うための作法が分からないから、今に至るまで上手く付き合えないでいると思うんですよね。本来なら、著者との方が付き合いづらいわけなんですが……(笑)。
出版業界の中で、「字が読めます」とか「文章が書けます」みたいなことは大した価値を持たないでしょう。でも、ビジネスの基本は「比較優位」だから、例えば中の上ぐらいのスキルを持ったプログラマーが出版業界に入ったらめちゃくちゃ役に立つはずだし、逆に中の上くらいの仕事ができる編集者は、IT業界とか他のリアルビジネスの現場でも役に立つはずで……そういう移動がしにくい現状が、僕はやっぱりもったいないなあと思っているんです。一冊の本を作るときに、「これはウェブサイトでこう展開してみよう」とか、「これは内沼さんに一緒に考えてもらって、ちょっと違う売り方をしてみよう」とか、そうやって自由度が増えていくといいなと思う。
小林:そういう意味で言うと、先ほど出た外商の話(2/5参照)ともつながりますが、出版社は「どこにお金をかけるのか」という配分を変えようという動きに対してすごく保守的なのかもしれない。
外部スタッフへの人件費や広告宣伝費がかけられない場合、どこに一番お金をかけるかと言ったら、本を「作る」ところに集中せざるを得ないんですよね。そこからプラスアルファで、どこかに予算を割り当てるというのは、基本的にない。
だから、やっぱりどんな出版社も編集者も営業マンもみんな、そういう新しい出会いを待っていますよね。それは確実だと思う。
仲俣:僕も「編集者/ライター」という肩書きの他に「本屋」としての名刺も作ろうと今夜は思ったくらいです。普段、書評を書くことやトークイベントをやること、何か企画をすることが、本を売ることにつながっているという意識はあるので、それを「本屋」だと言ってしまった方が楽だなあと思って。だから僕は「本屋」になると決めました。
小林:まあ、『本の逆襲』がちゃんと売れることが、内沼さんの正しさを証明することになりますね(笑)。
内沼:いや、あの、どのくらい売ればいいでしょうか……(笑)。でも自分で言うのはなんですけど、この本をたくさんの人に読んでもらえれば、きっと今よりも少しは、本の世界が面白くなると信じています。
小林さん、仲俣さん、今日はありがとうございました。
[イベントレポート「逆襲する本のために」 了]
構成:後藤知佳(numabooks)
編集協力:川辺玲央、松井祐輔
[2013年12月11日 B&B(東京・下北沢)にて]
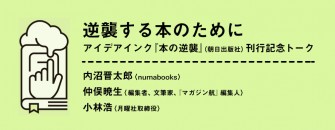












COMMENTSこの記事に対するコメント