2013年12月、朝日出版社のアイデアインクより出版された内沼晋太郎(numabooks/DOTPLACE編集長)による著書『本の逆襲』。その発売当日に、内沼の活動を古くからよく知るお二人(編集者/文筆家の仲俣暁生さん、月曜社取締役の小林浩さん)と著者との間で交わされた鼎談の模様をお送りします。無限に拡張していく「本」の概念。『本の逆襲』を起点に、三者それぞれの視点から、“逆襲”はいかにして可能かを探っていきます。
★2013年12月11日、本屋B&B(東京・下北沢)で行われた、内沼晋太郎『本の逆襲』(朝日出版社)刊行記念イベントのレポートです。
【以下からの続きです】
イベントレポート「逆襲する本のために」1/5
「本屋」はいわゆる「書店」とは別のもの
仲俣:僕は下北沢に住んでいるのでB&Bにもよく来るし、さっきのボイジャーさんのWebマガジン「DOTPLACE」は、僕のやっている「マガジン航」とも兄弟誌みたいなものなので、よく内沼さんとはお話したりお目にかかる機会が多いんですけど、僕よりも早く内沼さんと知り合っている小林さんは、どんな風に内沼さんを見られているんですか。
内沼:怖いなぁ(笑)。
小林:『本の逆襲』をお読みになった方の中で、業界の中の方がいらっしゃるとしたら大抵は、この本で書かれていることを読むと「大体わかってるよ」って言うと思うのね。でも「大体わかってる」ことを自明のこととしないで、自分の実感で「それがどういうことか知りたい」と歩んできたのが内沼さんなんです。
最初僕が出会った頃は、もちろんまだ彼は大学を出たばかりの若い人で、業界にも一言言いたいことがあったんだろうけど、どちらかと言うと僕は内沼さんが多少ナマイキなことを言ってもそんなに嫌な感じはしなかったのね。内沼さんよりもっと嫌な感じに聞こえる人はいるわけで……それはもう、内沼さんのキャラクターの良さなんじゃないかなって。
内沼:当時は特に何の実績もありませんでしたから、もしそうだとしたら完全にキャラクターで乗り切ってきたのだと思います……。
小林:キャラで得してる部分はもちろんあるんだけど、自明のことを「自明だからこの件は話さなくていい」としなかったのが、この本の成果にもなっている。提示されている10の考え方(『本の逆襲』第3章「これからの本のための10の考え方」)の中には、細かく辿っていくと綻びがないこともないけど、それは内沼さんの綻びというよりも、実際に出版業界が持っている綻びでもあって。
この本で僕がすごく面白いと思ったのは、最後に「あなたも『本屋』に!」っていう呼びかけがあるじゃないですか。ここで言う「本屋」はいわゆる「書店」とは違うんだよね。
内沼:さっきお話した『BRUTUS』の本屋特集を作ったときに、鳥取にある定有堂書店さんという本屋さんを訪ねたんですが、そこの店主の奈良敏行さんという方が「『書店』というのは、本という商品を扱い、陳列してある空間のこと。広ければ広いほどいいし、それに合わせてサービスの質を向上させていくもの。対して『本屋』というのは人のことだ」とおっしゃっていました。「本好きな人というのは、自分という存在への関心が高い人なので、出会った本について人と語り合いたくなるものです。『本屋』というのはその媒介者であり、『本屋』という生き方が楽しい」んだと。
本の媒介者はみんな「本屋」だし、「本」はもう定義できないくらい拡張しているので、それを扱う人は当然増える。だからあなたも「本屋」でしょう、というようなことを『本の逆襲』では書きました。
小林:そこがね、僕は「思い切ったな」と思ったの。
僕は大学生を相手に、出版業界に関する講義をすることがあったんだけど、僕はそういう場では出版社の話はしても、「あなたも零細出版社を立ち上げてみませんか」とはなかなか言いにくいのね。でも実は以前に別の機会で話をしたときに、少し学生さんの感情に訴えたくて、「出版社、面白いですよ」ってあえて言ってみたんですよ。でもその後に、ものすごく後悔したの。なぜかと言うと、例えば自分の子どもが大きくなって「出版社をやりたい」って言ったら「やめなさい」って言下に止めると思うんですよ。商売として厳しいことがたくさんあるから。
だから僕だったらあえて言えないだろうな、ということを内沼さんは本の最後に持ってきている。最初から「この一言でバシッと終わるんだ」って決めて書いていたのかどうかがすごく気になって。
内沼:うーん……誤解を恐れずに言うと、この『本の逆襲』という本は、ある意味で啓蒙書なんですよ。僕は広い意味での「本」の未来は明るいと思っているし、それに関わる人を増やさなければ、それこそ僕の好きな「本」というものはなくなっちゃうんじゃないかと思っていて。割とシンプルに、今、小林さんがおっしゃったみたいに「みんなはやらない方がいい」と言って、実際に若い人が誰もやらなかったら、「本」はなくなってしまうという危機感を持っているんです。
みんな厳しいって言うけど、やり方は色々あるし、それで食べていかなくてもいい。例えば本の読み聞かせをする人も「本屋」だし、ブログで本の紹介をし続けている人も「本屋」だと思うんですよね。その人たちのおかげで、実際に本が売れていくことがあるわけですから。彼らのような「本屋」はそれで食べているわけではないけれど、それでもいいと考えれば、新しい「本屋」のアイデアは無限に出てくる。そういう全てに関わる人を含めて、「本屋」を増やすための啓蒙なんです。そのためにあったほうがよい知識を2章で、アイデアを出すための切り口を3章で、それぞれ書いたつもりです。最後に「あなたも『本屋』に」と言うのは、この本の基本スタンスとして、割と最初から決めてましたね。「みんなで『本屋』になろう、みんなで逆襲に加担しよう!」という。
小林:すごく共感するんですよね。往来堂書店の初代店長の安藤哲也さんは当時『本屋はサイコー!』(新潮社、2001年)っていう本を出していましたが、あの中でも言ってるんですよね、「君も本屋に」と。そしてその何年か後に、安藤さんはファザーリングジャパン(※編集部注:父親支援事業を行うNPO法人。2006年発足)を立ち上げた。それは「本から離れている」というイヤミな言い方もできるんだけど、内沼さんから見るとああいう展開というのも「本屋」の一形態で、それもアリなのかなと。
内沼:その通りです。安藤さんは今も現役バリバリの「本屋」だと思います。結成10周年を迎えられた「パパ’s 絵本プロジェクト」もそうだし、ファザーリングジャパンでは絵本の普及とか、父親として子供にどうやって絵本を読ませるかっていうことをやってらっしゃるので、むしろその辺の新刊書店で何も考えずにバイトをしている人よりは、超「本屋」ですよね。そういう人が増えるといいなと思っているので、安藤さんのことも本に書けば良かったなと今思ったくらいです。
「本屋」に必要なバイリンガル性
仲俣:「本屋」っていう言葉は、石橋毅史さんの『「本屋」は死なない』(新潮社、2011年)でも同じ意味あいで使われていますよね。書店が厳しくなっても、そこにいる人間としての「本屋」を彼は訪ね歩いていて、定有堂書店にも行っているから、内沼さんもまさに同じ言葉に影響を受けている。石橋毅史さんは元出版業界紙の記者だから、正式には出版業界内部の人じゃないんですよね。「自分はアウトサイダーだ」という気持ちがあったんだと思う。
内沼さんも出版業界の外の企業やプレイヤーと本の仕事をする機会が多いと思いますが、出版業界の中の言葉が外では通じないことも多い。だから一般社会の言葉に言い換えなくちゃいけなくなるけど、本の世界よりも社会全体の方がずっと広いわけだから、それも必要なことなんです。そう考えると、媒介者を通じて本を外の社会に広げていった方が、中だけの言葉とルールでやっていくよりも、遥かに未来は明るいと僕も最近強く思っているんですね。
でもそのためには、出版のうちと外の両方に通じる「言葉」を持ってなきゃいけない。バイリンガルじゃなきゃいけない。内沼さんの仕事がユニークなのは、本を語る内部の言葉をよく知っている上で、ビジネスなりブランディング、病院とかの公共的な場所も含めて、外に対して語れる言葉を持っていることです。
そういう風に考えると、「本屋」になるのはけっこう大変なんですよね。
小林:従来の書店業界の話からすると、書店って、お店を構えて本を売る「店売」と、お店の外――大学や図書館だったり――に行って本を売る「外商」という二つがある。内沼さんが今やっている、本屋さんの外で本棚や閲覧室を作ったりするブックコーディネイターの仕事というのは、従来の縦割りからすると「外商」的な仕事ですよね。
内沼:そうですね、「外商」だと思います。
小林:内沼さんにしても、BACHの幅允孝さんにしても、ご自身は「外商」の仕事をやろうと思ったんじゃないだろうけど、書店業界の外商担当者はその仕事を見て「あっ」ってなったはずだと思う。大学の先生や図書館を相手にしたり、街の喫茶店に雑誌を卸したり……といった地道な仕事とはまた別の「外商」の仕事があるということを業界人は発見――より正確に言えば再発見――したわけです。内沼さんはそんな意識はあったのかな。
内沼:そのことに気が付いたのは、結構後になってからです。
3年前の『BRUTUS』の本屋特集で、島根県の松江にある「アルトスブックストア」さんに取材させていただいたときに、アルトスさんが店以外――つまり外商でも売上を上げていた。病院の待合室の本棚をコーディネイトしたり、近隣の学校図書館に出入りしておすすめを買ってもらったり、近くの高級スーパーの中の雑誌売り場なども手がけられたりしていて、似た仕事ですね、という話になった。そのときにあらためて、自分の仕事は出版業界では「外商」に近かったんだと気がついたんです。
いわゆる「外商」と違うのは、何でお金をもらっているかです。外商の利益は基本的に本を売って得る利益ですが、僕はたいていの場合は本の利益はもらっていない。僕は本を並べたいという人に、なぜ、何のために、どんな本を並べたいのかをヒアリングして、それに対して流通からセレクトまで最適な提案をすることに対して、フィーとしてお金をいただいていることが多いです。
でも、書店の外商担当の人が、例えば大学の先生向けに本を選んで持っていくのにも、本当はセレクトのコストがかかっているんですよ。かかっているはずなんだけど、昔から書店は、そこではお金を取ってこなかった。僕たちはそうしたコストがあまりに大きい案件に対して、それに見合うフィーをいただく代わりに別の価値を提供するという仕事を、気づいたらやっていた。結果的にそうなったという感じで、従来どうであるとかは意識していませんでした。
仲俣:内沼さんがやっていることは、出版業界のルールを破った破天荒な行為のように言われるかもしれないけど、業界の中にいる人にとっては、実はすごく理解できることでもある。
実際、本を売ったお金の2割くらいのマージンだけじゃやっていけないなら、それ以外の「どうやって本を読者に媒介するか」というサービスの部分でもお金を取るべきなんです。もちろん本屋は入場料金をとらずタダで入れる場所だけど、そのことですでにサービスが発生しているわけです。そういう試みを、具体的な行動で示している人だと思うんですよね、内沼さんは。
外商といえば、『本とコンピュータ』の中で一回だけ作家の橋本治さんに書いてもらった原稿があって、平凡社ライブラリーの『浮上せよと活字は言う』(平凡社、2002年)に収録されているんです。その原稿(「産業となった出版に未来を発見しても仕方がない」)の中で橋本さんは「本屋はこれから富山の薬売りになればいい」というようなことを書いているんですね。
それにいまの出版社だって、本業の出版以外に採算部門を持っているところはけっこうあって、実はそこでは社会とつながってる。「ピュアな本と出版と本屋さんだけで出版産業が成り立っている」というのは幻想だし、業界内の人もそれを知っているのに、まるで社会と隔絶して出版業界ができているような演技をずっとしてきたところがあるでしょう。でもそうじゃない、というのが本当なんだから、そういう意味でも内沼さんのやっていることはすごくリアルだし、出版業界の中/外を分けずにコミットできる部分だなと思いますね。
内沼:そうですね。僕は最初にお話したみたいに、まずやってみる、ということからはじめていて。今、仲俣さんや小林さんがおっしゃったような出版業界の内側のことは、ほとんど後から、やりながら知っていったんですよ。だから最初のうちは本当に無防備でした。知り合った業界の人から話を聴いて、おそるおそる自分の活動について説明するための言葉を補強して、また新しい活動をはじめて……と繰り返していって、気づいたら10年経っていた。そして自分で新刊書店をオープンしてやっと、少しは胸を張って言える実績と知識とが伴ってきたので、仲間を増やすためにこの『本の逆襲』に、ぼくが得てきたものを文字数の許す限り全て書いた、という感じです。
[3/5へ続きます](2014/1/10更新)
構成:後藤知佳(numabooks)
編集協力:川辺玲央、松井祐輔
[2013年12月11日 B&B(東京・下北沢)にて]
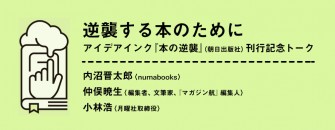












COMMENTSこの記事に対するコメント