大山エンリコイサム+寺井元一
「ストリート・アートと公共性
――表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで」
ストリートにおける表現活動とまちづくりは、これまで、そして今後どのように共生していくのか? 千葉県松戸駅の半径500メートルを「MAD City」と名付け、アーティストやクリエイターを誘致してまちづくりを行う「まちづクリエイティブ」の代表・寺井元一さんと、MAD City内のアトリエにかつて入居していた美術家であり、グラフィティ文化に関する論考集『アゲインスト・リテラシー』を2015年に上梓した大山エンリコイサムさんが対談を行いました。
●本記事は、2015年5月23日に本屋B&B(下北沢)にて開催されたイベント「ストリート・アートと公共性 表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで ――『アゲインスト・リテラシー グラフィティ文化論』刊行記念」を採録したものです。
●連載「アソシエーションデザイン つづく世界のつくり方」本編はこちら。
[1/4]
合法的にストリート・アートの発表ができる場を

(左から/敬称略)大山エンリコイサム、寺井元一
大山エンリコイサム(以下、大山):本日はご来場ありがとうございます。アーティストで、『アゲインスト・リテラシー ――グラフィティ文化論』(LIXIL出版、2015年/以下、『アゲインスト・リテラシー』)の著者の大山エンリコイサムです。よろしくお願いします。
寺井元一(以下、寺井):寺井元一と申します。よろしくお願いします。僕は、まちづくりを行う会社、株式会社まちづクリエイティブ(以下、まちづ社)の代表です。その事業のなかで、「MAD Cityプロジェクト」という千葉県にある松戸市内の半径500mほどの範囲に、もうひとつ仮想的に街をつくる活動をしています。
つくると言っても、もともと現実に存在する街に被さるかのように、架空のエリアをつくるという話です。具体的には、空き家などの空いている不動産を使い、そこに新しい事業を入れて住民や店舗を増やし、街のローカルルールや文化を創るというようなことをしています。たとえば、築100年ほどの商家を物件として扱い、現在20人ほどのアーティストやクリエイターたちが、その建物にアトリエを構えています。この「古民家スタジオ 旧・原田米店」を立ち上げたのが2010年ごろで、最初の入居者の一人が大山さんでした。ただ、初めてお会いしたのはもう少し前です。

もともと僕はアーティストと一緒に何をやっていくかを考える活動をしていました。それが、今でもまだ代表を務めているNPO法人「KOMPOSITION(コンポジション)」です。このNPOは2002年に法人化されました。KOMPOSITIONのプロジェクトで、今も続いていて世の中に多少知られているものは、「ALLDAY」という、代々木公園で行われる日本でも最大規模のストリートバスケットボールの大会かと思います。
そのKOMPOSITIONで最初に立ち上げたのが、「リーガルウォール」という、グラフィティやストリート・アートをやっている人たちが、合法的に自分の作品を発表できる壁を街中にどんどん作っていくという活動です。大規模なものですと、渋谷の東急ハンズのちょっと先にあるビルなどで、建物全体に絵をかいてもらいました。OS GEMEOSさんとか、HITOTZUKIさんといった方や、普段は夜中にかいているグラフィティ・ライターの人たちも含めて、さまざまなアーティストが自分たちの作品を発表できる場所を、街をジャックするかたちでどんどん作っていこうと活動していました。

渋谷川リーガルウォール(2004年制作、現存はせず)。地域住民の願いによる「渋谷川の環境再生」をモチーフに制作された

渋谷区宇田川町のリーガルウォール(2005年制作)
5000平米の巨大な壁面をオープンに ――桜木町 ON THE WALL
寺井:このあたりのさまざまな活動を手掛けさせてもらった結果、僕の方でも集大成的なイベントがあって、それが2007年の「桜木町 ON THE WALL」でした。
大山:寺井さんとは桜木町 ON THE WALLで初めて仕事しましたね。その前から知り合いで、20歳くらいのときからKOMPOSITIONの活動は知っていたし、事務所に遊びに行っていました。
寺井:桜木町には、ものすごい大きな壁画地帯があります。もともと東急電鉄が持っていたものを横浜市に渡し、横浜市が運営することになりましたが、市となると、もともとあった多くのグラフィティなどをどうコントロールしていいかわからないので、一度美大生やウォールペイントアーティストのロコサトシさんに上から絵をかいてもらったときに、グラフィティのコミュニティがものすごくバッティングしていて、上から全部つぶされるという事態が起きたんです。
折り合いがつかないので僕らが呼ばれて、「1.5kmほどある大きな壁面のかき換え」というかたちでアートイベントをやってくれないかと話をいただき、引き受けることになった。その地域は、横が6m、高さが5mほどの壁が約170面ほど続いているんです。面積としては5000平米ぐらい。この170面をどうやって埋めようかと議論になったときに、グラフィティの方の文脈も大切にしつつ、一方でペインター、アーティスト、近隣の方々も含めいろんな方がオープンに参加できるような仕組みをつくる方向性で進めていきました。
公募を行って、大山さんにも参加いただくことになったんです。今も覚えてるんだけど、銀色のPOSCAのようなもので延々とかいてましたよね?
大山:クロムの三菱ペイント・マーカーを大量に使ってかきました。
寺井:下にいっぱい落ちてましたよ。かいているときにどんどん使い切って、足元に10本、20本と溜まっていました。
大山:日の終わりに拾って帰っていました。ポイ捨てはしていないです(笑)。
寺井:(笑)。このようにいろいろな方がいました。近隣の小学生がお父さんと一緒にかいていたり、日本のグラフィティ界のレジェンドのようなKAZZROCKさんが参加してかいてくださっていたり、そのような状況のなかで大山さんともご一緒したんです。
大山:こういうプロジェクトでの寺井さんの立ち位置というのは、アーティストと行政というふたつの対照的な人格のあいだでネゴシエーションすることです。社会のなかでアートを動かすということをずっとやっているわけです。それは「ジェントリフィケーション」[★1]の現場に立ち会っているとも言えますし、グラフィティ文化というニッチなサブカルチャーを、法やモラルで固められた社会空間に、微調整しながらいかに着地させていくかという実践でもあります。
『アゲインスト・リテラシー』では、グラフィティ文化やストリート・アートがニューヨークで行政やコミュニティとどう関わっているかというのがトピックのひとつなので、そういった関心から今回一緒に対談しようと思いました。
★1│ジェントリフィケーション:都市において、比較的低所得者層の居住地域が再開発や文化的活動などによって活性化し、結果、地価が高騰すること(現代美術用語辞典ver.2.0より)。
新天地・松戸での最初のプロジェクト
「”MAD WALL” Project in Matsudo」の際の記録映像(2010年)
大山:これ(上記動画)は千葉県の松戸市で、寺井さんのプロデュースのもと、オランダのZEDZというグラフィティ・アーティスト、そして日本人のペインターのMHAKと僕の3人で制作した壁画の記録動画ですね。
寺井:リーガルウォールの集大成のひとつとして桜木町 ON THE WALLをやって、実は少し燃え尽きたところもあったんですね。行政などの方々と、グラフィティやストリート・アートの方々とが、公共空間を通じて共存できる仕組み作りにずっと関わりながらも、双方の距離感がだんだん深刻化して僕らじゃとても手に負えなくなって……。対話よりも管理、規制緩和よりも規制強化が、誰にも悪意がないのに進行していく都市の病理を目の当たりにしたんです。最終的に、渋谷にはいたくない、この社会では活動を続けられないと考えて、新天地を探し、松戸に向かったときに最初に実現したのが実はこの壁画のプロジェクトだったんです。僕にとっても、新しい始まりになるものをなんとか作れないかと考えました。インタビューのときに、「これまではアーティストのためにやっていたけど、これからは街の人のためにもやる」と言ったことなんかも非常に思い出深いです。

「MAD WALL」(2010年制作)
面白いのは、のちにこの通りの名前が「根本壁画通り」へと変わったことです。壁画があることで、この通りの名前を変えたいと地域の方々が考えてくれて実現しました。そういう意味では、渋谷に根付くことはできない、壁画ができても何も変わらないと苦しんで松戸にやってきて、壁画ができたら街の名前そのものが変わったという一件が起きたのは、ひとつの成果だったのかもしれない。

「根本壁画」(2011年制作)。「MAD WALL」の反対側が使用された
今日お話するのは、これは2010年の話だから、じゃあそれから5年経ったけど、この先はどうなのですか? という話かもしれないです。いずれにせよ、ストリート・アートやグラフィティのようなものに対し、僕はアクターというよりはどちらかというと裏方としてずっと関わってきた立場の人間です。
日本におけるグラフィティ文化への理解を底上げする
寺井:大山さんに『アゲインスト・リテラシー』の概要を簡単にお話しいただいてもよろしいでしょうか。
大山:基本的にはグラフィティ文化の歴史を辿りながら、それを同時代性のなかで考えていくという内容です。批評家視点の部分もありますが、僕はアーティストなので、最終的には作家としてのステートメントに舵を切っている。つまり著者としての僕の立場も複合的で、そういう意味でもいろいろなものが詰められた本です。そこで、章立てを説明するのがわかりやすいかと思います。

『アゲインスト・リテラシー ――グラフィティ文化論』(LIXIL出版、2015年)
4章あるのですが、第1章は「作家論」です。グラフィティ文化あるいはストリート・アートと呼ばれるジャンルに属する作家を8名取り上げ、ひとりずつ丁寧にフォーカスし、その作品や実践を批評的に論じています。
第2章「都市と落書きの文化史」では、1章の前提となるグラフィティ文化の歴史や、過去の落書き現象の文脈に触れていきます。いわゆるグラフィティ文化やストリート・アートは70〜80年代のニューヨークで誕生しますが、それ以前のさまざまな落書きの文化史を20世紀初頭まで遡り、検証を加えながらアメリカという国、またはニューヨークという土地に埋めこまれた落書きの遺伝子を掘り起こしています。たとえばホーボーと呼ばれる流浪の民が、大恐慌時代のアメリカで名前の落書きを大陸横断鉄道に残した話とか、1940年代のニューヨークでスパニッシュ・ハーレムの路上に落書きしていた子供たちの話とか、さまざまな事例から特徴を抽出し、それらが70年代以降のグラフィティ文化に多層的に流れこんでいるという考察を展開しています。
第3章「現代日本との接点」では、現代日本の文化や状況論と比較を試みています。グラフィティ文化の分析から得られた知見を応用しながら、オタク文化やライヴ・ペインティング、そして東日本大震災について考えています。
第4章「美術史に照らして」では、60年代ニューヨークの美術批評にクローズアップし、そこで考えられていたことを、1章・2章で扱ったグラフィティ文化の議論に照らし合わせ、当時の美術批評の問題を拡張的に解釈することで、ふたつの文脈を交差させています。そしてその流れのまま、僕自身の作品についても触れています。というのも、僕も「ストリート文化」と「現代美術」というふたつの領域があるとしたら、そのあいだで活動している部分があるので。
寺井:第2章は、圧倒的に調べただろうな、という印象を非常に受けます。日本の人間でここまで調べた人はそういないでしょう。

大山:英語文献はある程度ありますが、社会学的な研究が多く、文化史として大きなヴィジョンを描いているものは少ないです。『アゲインスト・リテラシー』では先行研究を踏まえつつ、さまざまな落書きの文脈を組み合わせて、僕なりにもう少し大きな物語を紡いでいます。この本に個性があるとしたら、その点でしょう。
ただ、批評の理念に終始するのではなく、実際にこの本が出版され、こうしてトークに皆さんが参加してくれたり、アートの展覧会やグラフィティの企画を手がける立場の人が参考にしてくれたり、そうやってこの本で論じていることが実際の社会のなかで実践として機能していって欲しいと思っています。なぜなら、そもそも僕がアーティストなのに積極的に文章をかいている理由のひとつとして、日本におけるグラフィティ文化の理解を底上げし、僕自身の制作活動の背景をよりよく知ってもらいたいという実践的な動機があるからです。
そこで寺井さんみたいに、実際に社会実践として行政と関わりながら仕事をしている方の視点から、この本がどう役に立つか伺ってみたいです。
寺井:この本を批評として読み解くアプローチもやり方としてはあるし、この本を踏まえて、では自分たちの生活や日常に落とし込んだときに何が起きるのだろうか、どういったことが考えられるのかということは僕も読みつつ思っていました。今日はそういう話にも展開できればと思います。
とは言いながら、もう少し『アゲインスト・リテラシー』の内容を掘り下げさせてください。いくつか興味あることを聞いていきます。
語りづらさをバネにする批評的想像力 ――グラフィティ文化と東日本大震災
寺井:第3章で、震災に絡めて「AUS」の話を出していますが(p.192〜204「匿名性の遠心力 ――震災から考える」)、エッセンスとしてはどういうことを取り上げようとしたのですか。
大山:その章では「語りづらさ」がひとつキーワードになっています。前提を簡単に説明すると、グラフィティ文化は「匿名性」という言葉でラベリングされてしまう局面が多いんですね。コミュニティのアウトサイダーにとって、多くの場合、それは誰がかいているかわからないからです。しかし、それが何かを主張していることはわかる。そこでポリティカル・コレクトネス的に「この人たちは匿名の声なき声を発している。それに耳を傾けないといけない」といった思考回路が一元的に強くなる。
実際は1章で論じているように、アーティストによって作家性や方法論はじつに多様で、匿名性の一言で片付けられるものではありません。ですが、落書きというのは本人不在で痕跡が残っている状態なので、いわば欠席裁判が横行します。「これは匿名である」と勝手に言えてしまうわけです。そうすることで、グラフィティ文化やストリート・アートの豊かな多様性は捨象されてしまうのですね。そのことに抵抗したいのが、まずひとつです。
同時に、対照的な現象もあります。当事者性が強く、「やってない人にはわからない」「部外者が語るな」という反知性的な拒否力も高いんです。僕はこのふたつの現象は陰と陽だと思っていて。アウトサイダーによる「匿名性のラベリング」と、インサイダーによる「当事者性の特権化」という強い磁場によって、グラフィティ文化をめぐる批評的な議論がとても貧しくなっています。
アクロバティックですが、グラフィティ文化を語るときの以上のジレンマを、震災について考える手がかりにしてみたかったんです。震災をめぐっても当事者性の問題がありました。「東京は被災地なのか」「被災者でない人間はどう発言すればよいのか」「アートは震災を主題にすべきなのか」といったことですね。そして津波による水死者のなかには、多くの身元不明者、つまり匿名のまま亡くなられた方もいた。
寺井:つまり、震災に直面して苦しんでいる人間が、「外から震災のことを語るな」というような話が、語りづらさや当事者性に結びつくということですか。
大山:グラフィティ文化の問題を論じつつ、同時に震災について考えようとするとき、匿名性や当事者性の概念をモチーフとして両者を重ねることができるような気がしたんです。ただ、匿名性という言い方だと、死者の表象不可能性を括弧にいれて概念で代替し、語りやすくしてしまう。現実の人間関係やコミュニケーションにおいては、ためらいや疑念を含んだ「語りづらさ」の方がリアルです。

本書の内容に移すと、被災地を訪れたとき、瓦礫の山のなかにスプレーでかかれた「AUS」という文字を見つけたんですね。それが何なのかよくわからなかった。グラフィティのタグともちょっと違う。もしそれが津波に呑まれる瞬間に被災者が刻んだダイイング・メッセージだとしたら、恐ろしくて親族でもない僕は語れないわけですが、見たところ震災後にかかれたのは間違いなくて。被災地というコンテクストが詰まった空間にありながら、AUSはそこに馴染まずによくわからないものとして浮遊していたんです。その語りづらさは、震災そのものの語りづらさとは微妙にずれていた。つまり、意味がはっきりした震災という大惨事の重い語りづらさに対し、意味のわからない不思議な語りづらさが不意に出現した。それをバネにして想像力を飛躍させることで、なんとか震災に言及することはできないか。そういう試みでした。
寺井:それが「SOS」だったら語れないということですね。
大山:そうですね。AUSはただ即物的に匿名なものとしてそこにあって、周囲には被災とか津波とか地震などの意味が浮いている。そこで論理とか実証ではなく、批評的な想像力を媒介にして、AUSからたとえばポンペイに思考を飛ばしてみるわけです。ポンペイと東北は、事実関係としての結びつきはないけど、ともに自然災害の被災地で、また落書きが発見された場でもある。あくまで思考実験ですが、グラフィティ文化やストリート・アートについて考えるときも、匿名性や当事者性を超える想像力の飛躍を鍛えていく必要があるんじゃないか。そういう思いがありました。
寺井:面白いですね。
[2/4「『やれない理由はそこにはない』というその様が、僕にとっての『ストリート』かもしれないですね。」に続きます]
構成:吉崎香央里、後藤知佳(numabooks)
取材・撮影・編集:後藤知佳(numabooks)
(2015年5月23日、本屋B&Bにて)
[「アソシエーションデザイン」関連イベントのお知らせ]
林暁甫×寺井元一「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」
「混浴温泉世界」(別府)、「鳥取藝住祭」(鳥取)に加えて、直近では六本木アートナイト、同じく六本木での「リライトプロジェクト」など、地方と都心を横断してアートプロジェクトに関わってきた林曉甫さんをゲストに招き、地域アートプロジェクトについて考えるトークイベントを行います。
開催日:2016年4月29日(金・祝)15:00〜18:00(14:45受付開始)
出演:林曉甫(NPO法人inVisible)、寺井元一(MAD City/まちづクリエイティブ)
定員:30名 ※定員を超えた場合、ご予約の方を優先いたします。また、立ち見の場合がございます。
参加費:1500円(1ドリンク付き)
会場:FANCLUB(JR/新京成線松戸駅徒歩2分)
主催:株式会社まちづクリエイティブ
協力:DOTPLACE
★イベントの詳細・ご予約はこちらのURLから(ご予約は前日まで受付中)。


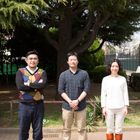











COMMENTSこの記事に対するコメント