林曉甫(NPO法人inVisible マネージング・ディレクター)
+
寺井元一(株式会社まちづクリエイティブ 代表)
「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」
近年増加の一途をたどり、もはや数え切れないほどの現代芸術祭が全国各地で開催されている現在。2016年は、それらに参加するアーティストや運営者のモチベーション、あるいはアートプロジェクトを呼び水にしたまちづくりが孕む問題を扱った論考・インタビュー集『地域アート 美学/制度/日本』(藤田直哉・編著/堀之内出版)などの書籍も刊行され、それらにまつわる議論が活発化した年でした。
アートプロジェクトを企画し実現させる現場の人々は、実際のところその動きをどう見ているのでしょうか? 「混浴温泉世界」(大分県)や「鳥取藝住祭」(鳥取県)、「Relight Project」(東京都)など、さまざまな地域でアートプロジェクトの企画・運営に携わってきた林曉甫(はやし・あきお)さんをゲストに迎え、千葉県松戸市でアーティスト・イン・レジデンスなども展開しながらまちづくりを推し進める「まちづクリエイティブ」代表・寺井元一(てらい・もとかず)さんと行った対談の模様をお届けします。
●本記事は、2016年4月29日にFANCLUB(松戸)にて開催されたイベント「地域アートプロジェクトとアソシエーションデザイン」を採録したものです。
●連載「アソシエーションデザイン つづく世界のつくり方」本編はこちら。
[前編]
アートと地域の「あいだ」にいる人たち
寺井元一(以下、寺井):「まちづくり」とか「地域アートプロジェクト」に関する話が最近よく取り沙汰されますが、アーティストじゃなくてコーディネーター/キュレーターといった「あいだ」の立ち位置にいる人の可能性について話せるといいなということで、今日は複数のアートプロジェクトの企画・運営に関わってきた林曉甫さんをお呼びしました。
林曉甫(以下、林):林です。アートプロジェクトの企画・運営は学生のとき以来ずっと、なんだかんだ10年弱やってますね。僕はもともと東京出身で、大学から大分県に行って、在学中に現地のアートプロジェクトに関わりはじめました。卒業後も続けて、フリーになったのが2013年。去年(2015年)、「NPO法人inVisible(インビジブル)」を作って、そこでも変わらずそういう活動をやっているよ、というのが平たい説明ですね。
これまで関わってきた企画はいろいろあるんですが[★1]、今日は「混浴温泉世界」と「Relight Project(リライト・プロジェクト)」の事例を通して自己紹介をさせてもらいたいと思います。
林:「混浴温泉世界」というのは、2009年から2015年までの間、3年ごとに大分県別府市で開催された芸術祭の名前です。この芸術祭に向けて国内外からアーティストを招聘して、いろいろなところと折衝をして、作品を準備していくのにだいたい1年半ぐらいかかります。展示場所のリサーチを経て、アーティストに下見に来てもらって調整し、作品の案を出してもらって、実際に作っていく、というような過程です。
混浴温泉世界を運営していた「BEPPU PROJECT」という団体は、2005年に別府でNPO法人として設立され、「いつかこの別府で芸術祭を実施する」というマニフェストを掲げて、それに向けて準備をしてきた団体です。いきなり「芸術祭をやります」と言うのではなくて、小さいアートプロジェクトを積み重ねていって、年間100日くらいさまざまなプロジェクトを実施していって、2009年に混浴温泉世界という形になった。その当時、僕はもう大学を卒業していたので、混浴温泉世界の事務局のスタッフとして、海外から来たアーティスト8組ぐらいの企画・制作をすべてやっていました。
例えば、2009年のときのチャン・ヨンヘ重工業(YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES)の作品では、街の中にメッセージボードを貼ったり、映像のインスタレーションを設置したりしましたね。フィールドリサーチを経て、彼らが別府を体験した中で得たインスピレーションや別府の歴史をもとにして作った作品です。

チャン・ヨンへ重工業「HONEYMOON IN BEPPU」(2009年)
別府ってもともと観光地としてだけじゃなくてハネムーンで訪れる人がいて、チャン・ヨンヘは男女二人がハネムーンで別府に行った記憶を回想する作品を制作しました。
寺井:作家がフィールドワークをして、こういう映像になったんですか。
林:作品中で話されていることは完全なフィクションなんだけど、「別府にはいろいろな立場の人が来てたよ」みたいなことは彼らに伝えてましたね。別府では砂湯というものに入れるんですけど、この作品の中にも途中で砂湯のシーンが出てくるんです。フィールドワークのときにアーティストが砂湯に入りたいって言うから、僕も一緒に入りつつ居合わせたおばちゃんと長々と話していたら、アーティストがのぼせちゃって。「お前がずっとしゃべってるから、俺はのぼせた」ってアーティストに怒られた(笑)。でも、後々作品を見たらそのシーンがばっちり使われていて、「やっぱり良い体験だったじゃん」って。
寺井:強烈なインパクトがあったということですね。
地域アートプロジェクトの数値的成果
林:で、芸術祭にまつわる数字も今日は持ってきたんだけどね。
寺井:生々しい!(笑)
林:一応、基本的には公的なお金で運営してるから、実行委員会形式でやっていって「地域にこれだけの経済波及効果があったよ」とか報告しますよね。このときは「日曜美術館」(Eテレ)が45分の枠で取り上げてくれて、メディア露出効果のようなものもかなりあったから、「この企画を通して地域がこう紹介された」とか。他にも副次的なこととして、このとき展示していたマイケル・リンの壁画が美術の教科書に載ったり、創造都市の分野で表彰されたり――情緒的な感動だけじゃなくて、数字的にはこういうことがありました、と[★2]。

★2:混浴温泉世界2009の数値的成果(BEPPU PROJECT『別府現代芸術フェスティバル2009「混浴温泉世界」事業報告書』p.19〜20より)
で、2回目(2012年)の来場者数はおよそ11万人[★3-1]。1回目(2009年)の来場者数は約9万人だったので、人数的には少し増えたということなんですけど、でも、この約11万人と、同時開催していた「ベップ・アート・マンス」(※別府市内で2010年より毎年開催されている公募・登録型の市民文化祭)の約5万人は重複しているところも多いから、正確にトータルで何人かというのを出すのは難しいんだけど、一応回収したアンケートの結果からはこういう数字が出ています。観光客としてこの人数が平均どのぐらい消費しているか、もちろん厳密にはわからないので、観光消費額についてはひとまず一般的な方程式に則った計算だとこのぐらいですよ、ということ[★3-2]。それから、「日曜美術館」がなかったということで、メディア露出広告換算の額は前回に比べると下がっています[★3-3]。

★3-1:混浴温泉世界2012の来場者数(BEPPU PROJECT『別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」・ベップ・アート・マンス2012事業報告書』p.21より)

★3-2:混浴温泉世界2012の観光消費額(BEPPU PROJECT『別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」・ベップ・アート・マンス2012事業報告書』p.74より)

★3-3:混浴温泉世界2012のメディア掲載実績・広告換算(BEPPU PROJECT『別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」・ベップ・アート・マンス2012事業報告書』p.72より)
寺井:僕も過去に「松戸アートラインプロジェクト」というものをやって、来場者数としては結構良い数字が出たんですよ。それはまあ、道路や公園などにも作品を配置したからというところもあって。そもそも一定の動線上に仕掛けを施せば来場者のような数字は作りやすい。そういう数字のカラクリがある以上、形式的に必要な成果指標は扱いつつも、本当に大切な指標が何かということも考えていかなきゃな、と思うんです。混浴温泉世界も2回目はメディア露出の数字が落ちたわけですよね。それを見て「じゃあやめた方がいいよね」みたいなことを言う人も出てくるんだけど、やっている側は「むしろ今、価値をいっぱい生んでるのに」と思っていることも多い気がします。
林:成果指標の開発は確かに重要です。尺度の問題なんですよね、結局。だから、どういう尺度で我々が社会を考えていくのか、その評価の指標や方法に対して、もっと多義的な話がされないといけないですよね。
寺井:混浴温泉世界の予算規模は、全体でどれぐらいあったんですか?
林:2回目(2012年)の予算は1億2000万とかで、1回目(2009年)が6,000万ぐらい(※別府現代芸術フェスティバル2015「混浴温泉世界」プレス資料 p.24より)。アートプロジェクトとしては弱小ですね。
寺井:それで弱小だというとビックリする人も多いんだろうなと思いますが、大規模な芸術祭はだいたい数億円を使ってますよね。
林:基本的に、ファンドレイズ(資金集め)はすごく草の根的な方法でやってました。文化庁から予算の半分ぐらいをもらったとしても、清算払いになるから運営資金を調達しなければいけない。そのために代表が自分の家を担保に金を集めてくるということもあった。金払えないなんてことばかりで……動けるモデルをきちんと作る前にいろいろ走らせてたから、大変でしたよね。
寺井:あるあるですね……(笑)。
林:そうして集めたお金のほとんどは、作品の展示場所を借りたりというような、プロジェクトに対しての予算です。混浴温泉世界は基本的に実行委員会形式を取っていて、その事務局はBEPPU PROJECTが回す。いろいろな場所からお金を借りてきたり、助成金を申請したりといったファンドレイズも、基本的にBEPPU PROJECTがやる、と。
その中で、地元の銀行さんがすごく良い形でNPOへの融資制度を組んでくれたりして、回転資金を獲得できたというのがありましたね。貸し方とか金利も含めて融通を利かせてくれた。それがその後にもつながったし、そういう意味では本当に大分のいろいろな方が芸術祭に可能性を感じて動いてくれたから実現できた芸術祭だった。実行委員会形式ってそれが本来の形なんだと思うんだけど、何とか実現させるために、かなりいろいろな場所がいろいろなリスクを取ってくれていたんですね。
BEPPU PROJECTはまちづくりを目的に掲げていない
寺井:2015年の第3回目で、混浴温泉世界がいったん終わったわけじゃないですか。その先はどうしようという話は今あるんですか。
林:俺もBEPPU PROJECTを離れて久しいから、そういう話を聞くような機会がなくて、現在のことは全然知らないんだよね。ただ、これは勝手な想像だけど、別府の観光業を支えていくためのインフラ的な組織や環境にアートが入っていくようなプロデュースをしていくんじゃないかなと思っています。温泉という別府観光の中心にアーティストやクリエイターが入って、場を作ったりするのはすごく良いなと。
寺井:芸術祭というものがまちづくりの最先端事例として紹介されるようになって、今やものすごく数が増えたけど、もともとあった「その街が持っていた産業とアートをどう結びつけていくか」みたいな議論が、5〜10年ぐらいのサイクルで今もう一度起きているのかな、と今の話を聞いていて思いましたね。
林:そうだね。BEPPU PROJECTって、まちづくりをまったく目的に掲げていなくて。「街のOSとしてアートが必要だ」っていうのはずっと言われていたけど、それは街そのものの体験をクリエイティブにするためであって、街を活性化させること自体を決して重視していない。「ここでしかできないアートプロジェクトや体験を作る」ということにミッションとしてはすごくフォーカスしていて、その結果として人が来るとか、来た人にこういう体験をしてほしいとか、別府ってこういう場所だよねというのを総合的にどうデザインするか。これこそが、ある種の“作品”だって提示しています。(まちづくりは)結果なんだよね、あくまでも。その視点は、まちづくりを第一に掲げているところとは違うのかもしれない。
寺井:もしかしたら、それより前にまちづくりをやっていた人たちとのシナジーが今ようやくうまく回りだして、次のステージに入ったというのもあるのかもしれないですよね。
林:まさにそうですね。別府の市長選挙で若い候補が当選したり、BEPPU PROJECT自体を取り巻く環境も政治環境とともに変わってきたというのはある。今は(熊本地震で)被災してしまったからその影響もあるけど、変化しているのは間違いないですね。
震災を経た後のパブリックアートを再生させる
林:そうして2回目の混浴温泉世界が終わって、報告書といった業務が終わったときに、「そろそろ別府以外でやるのもいいかな」と思ったんです。別に別府が嫌いだったわけじゃなくて、他のところでもアートプロジェクトをやってみたいという気持ちもあってBEPPU PROJECTから独立して、個人でいろいろな仕事を受けていたんですけど、去年(2015年)の7月に「inVisible(インビジブル)」というNPO法人を立ち上げました。
inVisibleは、都市空間においてのアートプロジェクトの企画を自分たちで実施していく、ラボ的な場所として位置付けています。他にも、いろんな場所でプロジェクトをやってきたので、そのノウハウを必要としているところに提供する中間支援事業などもしています。
今、具体的に一つやっているのが、東京都とアーツカウンシル東京と共催している「Relight Project(リライト・プロジェクト)」というものです。これは東京六本木にあるテレビ朝日の社屋の壁面に設置された、宮島達男というアーティストがつくったパブリックアート(「Counter Void」、2003年)なんですけど[★4]、東日本大震災以降はそれを消灯しているんですよね。
このカウンターの数字が9から1に減っていき、0が現れることなく消灯し、また9に戻っていく。生や死、再生をテーマにしている作品です。これをどういう形で再生させるかというプロジェクトを東京都とアーツカウンシル東京と共催しプロジェクトを進めています。震災から5年経って、3.11への想いや記憶が移り変わっていく中、問いや気付きの装置としてこの作品を再生させたいということで、3月11日から3月13日、「Relight Days」と名付けた3日間に作品を再点灯したんですね。宮島さんが2011年の震災のときにこの作品を消したのが3月13日だったので、11日からそこまでの3日間というフレームになったんですけど、再点灯を軸にしながら、その近くでワークショップやトークセッションをしたり、オンライン上などでもプロジェクトを展開していきました。
これが5年ぶりに再点灯したときの写真ですね[★5]。アーティストだけじゃなくて、いろいろなジャンルの人たちが社会とともに考える機会を設けました。関連イベントに参加したのは、3日間で650人ぐらい[★6]。
5年ぶりの再点灯ということでメディアにはたくさん取り上げられて、全国紙にも載ったりしました。それからTSUTAYAのような、地方だとつながらないようなところにプロジェクトを通じて関与してもらったりできたのは面白かったかな。
既に作られた作品をどう“使う”のか
寺井:作家の宮島さんがこのプロジェクトをどう思うかというのは結構重要なファクターだと思うんだけど、彼はそのあたりの動きに対してどう思っているんだろう。
林:宮島さんはすごくウェルカムでした。彼がいつも言うのは「自分にとっては嫁に出した作品だから、嫁がその後どうなるかというのはもう俺には決められない」と。何かしらの意見はあるかもしれないけど、それを決定できるのは作家じゃなくて、作品を取り巻いている人や環境だから。ただ、最初は宮島さんに「作品を点灯したらダメだ」と言われたんですね。そこで、そもそもどう点けるか/再点灯自体をどう考えるかをプロジェクトにしようという話になって、作家が作品に込めている思いだけじゃないところまで、少し抽象化された。
とはいえ、実は重要なのはコレクター(作品の所有者)であるテレビ朝日なんですね。宮島さんが「嫁に出す」と表現したように、作品が購入されて、今の場所に出した時点で作品の所有者はテレビ朝日なんですよ。作家へのリスペクトがあった上で、どうすれば今の時代で作品が機能するのかを考えると、もしかしたら日本中にある他のパブリックアートも、その設置の背景を調べたり、あるいは他のアーティストをぶつけることである種の舞台芸術のように作品を使って新しい演出をしたり――既に作られたものに対して、新たな形でアーティストを関与させ作品を現代に合った形に更新していく試みがもっと行われてもいいんじゃないか、と思います。
寺井:宮島さんも「嫁に出した」とは言ったって、その例えで言えば作品が自分の子どもであることには変わりないわけで、気にならないわけはない。「作品を見せる/見せない」という話はよく議論されると思うんですが、「どういう趣旨だったら使っていい/使ってはいけない」という議論もある。そちらの議論のほうが本質に近いはずだけれど、見逃されがちだと思います。“使う”という視点で作品を見たときに、実際どういう文脈がありうるのかということは重要なポイントだなと思いました。
林:アーティストがつくるフィクションや抽象的な形から、鑑賞者が何を掴むか。作品は作り手と受け手がいて成立するものだと思ってる。アーティストが作ったフィクションをなぞらえてみる。そのフィクションの中に投影されていることが、普段は考えもしないことだったり、何か普段と違う行動に移すためのきっかけになるとすごく感じていて。その一番の原型は神話にあると思っているんです。自分たちの生きている時間を超えた「社会の在り方や正しさって何だろう」ということを研磨していったときに残っているものが、神話と今呼ばれているものなんじゃないか。同じように、時代が変わっても通じるものがアート作品に宿っているのであれば、“使う”側がそれを引き受けてやっていく。これはすごく大事なことじゃないかなと思いますね。
寺井:一つぐらい、会場から何か質問ありますか? ……そちらの方、どうぞ。
質問者:「神話のように作品もアップデートしていく」という話に関してですが、アップデートすること自体は賛成だとしても、アップデートの方向性に乗れない人も中にはいると思うんですよ。そういう人たちに対する声って上がったりしないんですか?
林:「その方向性じゃないだろう」みたいな声が上がるかっていうことですよね。それはあるべきだと思う。今回のRelight Projectに対しても、「3.11に点灯する」ということに対しては、最後の最後までテレビ朝日が「視聴者の方からクレームが来るんじゃないだろうか」と懸念していたんですね。結局なかったんですけど。「常に一定数からは反対されるであろう」ということをおそらく考えているんですね。
アートって何かの問いかけの装置としては機能するとは思うんですが、僕らみたいに、街中や社会に対して何か語りかけようとする行為に、アートをある意味“使おう”としている側としては、批判が来ても何かの回答を示さないといけないなと思っているんですよ。少なくとも自分たちの気持ちの中では、拒絶ではなく、引き受けてちゃんと話をする準備はあるんですよね。それこそ昨今のインターネットでの炎上じゃないですけど、人の生命を脅かしてしまうようなことは別として、批判があるからと言ってやめてはいけないような気がして……。最近はそんなことを強く感じながらやってますね。
寺井:今の話は、藤田直哉さんが今年(2016年)の2月に出した『地域アート 美学/制度/日本』(堀之内出版、2016年/以下、『地域アート』)にもつながってくる気がします。
「地域アートプロジェクト」の定義
寺井:個人的には、「地域アートプロジェクト」が語られるとき、混浴温泉世界は代表的な事例の一つとして挙がると思うんです。越後妻有アートトリエンナーレも当然挙がる。ただ、六本木のRelight Projectは「地域アートプロジェクト」なのか、という一つの疑問が出てくると思うんです。開催されているのが都会のど真ん中だという感覚を持つからだと思うんだけど、中にいる人はそんなに違いを感じていない気もしていて。実際のところ、どういうことが「地域アートプロジェクト」の定義なんですかね。
林:カテゴリとか所属とかは考えたことがないけど、Relight Projectも地域アートプロジェクトの王道みたいなものは歩んでいるはずなんですよね、それが目立って見えていたかは別として。たとえば森ビルにしてもテレ朝にしても、関わっているパートナーは港区を本拠地とした企業だし。それからワークショップを区立の小学校でやったり、場所のリサーチをしに商店街に行ったり、学校帰りの地元の中学生が作品を観て「かっけー」って騒いでいたり――ある種、サイトスペシフィックに「この場所でしかできない」ということは重視しながらやっているから地域アートプロジェクトの事例集に入るものではあるはず。
寺井:実際に、そういう取材とかは来ました?
林:来てないですね。
寺井:やっぱりそうですよね。僕もRelight Projectは地域アートプロジェクトだと思っているんだけど、実際はそう感じない人が過半数なんじゃないかという気がするんですよ。
林:東京って実はすごく広いじゃない。青梅の方は人口減少しているけど、都心にはすごく人がいて、島嶼部だってあるし……全部「東京」って呼んでいるけど、厳密に見ていくとそれぞれの地域性があって、その個々の地域に向き合いながらそこでしかできない作品や体験をつくるプロジェクトは「地域アートプロジェクト」だととりあえず言ってみてもいいんじゃないかなと思います。
寺井:そうだよね。一方で、地域アートプロジェクトというもの自体は昔からあったんだけれども、こんなに各地にはなかった、というのが僕の認識です。数えてみると日本国内だけでも何百――1県あたり10以上はある計算――というぐらいにアートプロジェクトが増えていて、不思議な状況がある。これはどういうことかというと、芸術文化振興のためだけでなく、アートというコンテンツが結果的にまちづくりに利用されたり、まちづくりと一体になっているような状況がたくさん生まれている。
たとえば、美術館の中で行われる小規模な展示の話だったら誰もとやかく言わないかもしれないし、見に行きたい人が行けばいいだけの話なんだけれども、(現状主流になっている野外や公道なども使った開催形態になってくると)規模や影響力も大きくて、いろいろな責任も発生する状況じゃないですか。これは国立競技場の建設やエンブレムの問題から全部つながっていると思うんですけど、税金や公(おおやけ)性みたいなものがクローズアップされている中で、何か起こるたびにさまざまな人が「何でこんなことやるの」とか「意味ないでしょ」とかツッコミを入れてきて、アート側がそれに応えなきゃいけなくなっている。そもそもそういう状況にある地域アートの是非について、先の書籍の著者である藤田さんは問いかけているところがある。
アートプロジェクトは誰に向けられたものなのか
寺井:僕も過去に松戸でアートプロジェクトに関わっていたことがあるし、まちづ社(株式会社まちづクリエイティブ)でもアーティスト・イン・レジデンス的な動きをしているので、関係がないわけではないんだけど。別府や鳥取で芸術祭をやって、今はRelight Projectにも関わっている林くんは、今「地域アート」が批評されたり、ある意味叩かれたりしている状況で、どういうことを思っているんですか?
林:そうですね、当事者だからね(笑)。「地域アート」って名前で呼ぶとラベリングによってイメージがついちゃうから、「アートプロジェクト」という自分が呼んできた名前で呼ばせてもらうと――「アートプロジェクトって果たして誰に対してのものなのか」というのが一つの問いとしてありますよね。お客さんに対するものとして、ある種のエンタテイメント性を担保しなければいけないものなのか、あるいは一種の郷土芸能のように、そのコミュニティを円滑にしていくための役割を担うものなのか。もちろんプロジェクトに紐づくお金がどこから来ていて何を求められているのかということとも絡んでくるんですが、それでも、それぞれのアイデンティティがどこにあるのかということはすごく重要だと思っているんですね。
福住廉さんっていう美術評論家と僕は個人的な付き合いがすごく長いんですが、彼が越後妻有アートトリエンナーレの関連企画の一つの「里山の限界芸術」という企画のキュレーションをやっていたんですね。その中で切腹ピストルズというパフォーマーが、街の中をちんどん屋として練り歩いたらしくて[★7]。別に、それを見にわざわざ東京からハイセンスな人は来ないかもしれないけど、歩けなかった地元のおばあちゃんが、とにかく這ってでもそれを見たくて見る、という状況があって。
★7:2013年8月に「里山の限界芸術vol.4 野良着で逆襲!」展の特別企画の一つとして行われたパフォーマンス「切腹ピストルズ×会沢集落」。「松代の会沢集落に切腹ピストルズが赴き、草刈りと、音楽を打ち鳴らして練り歩きを行います。朝から参加できる方は一緒に草刈りしましょう。」(告知テキストより)
寺井:すごいなぁ……(笑)。
林:僕はその切腹ピストルズの作品は見てないし、どれだけのクオリティのパフォーマンスだったのかはわからないけど、もともと、その地域にはお祭りがあったんだって。でも今では担ぎ手がいなくなってしまった。そのパフォーマーはいろいろ考えた末に街の中を練り歩いたんだけど、そのとき福住さんは「それでいいんじゃないか」と思った、という話をしていて。
問われるクオリティというのは一体どこに対して、誰に対してあるのか。それは一律のものではなくて、その団体が持っている思想や方向性によって異なるけど、自分たちの中で明確に「これだ」と言えて行っていることが、一つの地域アートの例として批判的に見られるのであれば、僕はその批判に対して軽やかに笑いながらやっていればいいんじゃないかなと思う。「なぜやるのか」ということとの兼ね合いなんじゃないかな。表面的なところだけ見て批判されようと、やれば何かしら批判のようなものは来るので、それに対して過度に何かするというよりも、引き受けながら「自分たちにはこれがあるからやる」という風にしていくべきなのかなと。
公金を入れてアートプロジェクトをやること
林:基本的に、税金を使ってアートをやることにはすごく賛成なんですよね。“富の再分配”が、どうして文化の領域には投じられないのか?ということは常に思っているので。
たとえば仮に「文化面に税金をまったく使わない代わりに、税金を安くします。あなた方が希望するNPOに直接払ってください」という決まりにするんだったら文化面に投じられなくて結構だけど、福祉にしても教育にしても防災にしても何にしても、税金というのは社会に対して投じられるべきだから、自分が払っているからといって、必ずしも自分にすべての利益が入ってくるわけじゃないんですよね。文化に投資されて、そこでの活動が観光客を呼んでくるためのものとして成果を出しているんだったらそれでもいいと思うし、地域の中で断絶された世代間やコミュニティのつながりを作っていくのであれば、すごく価値があることなんじゃないかなと思います。
寺井:僕の理解としては、さっきのちんどん屋の話って、アートであるかという以前に「伝統芸能的なものをどう復活させるか」みたいな話にアーティストが手を貸した、という視点で読めるのかもしれない。「うちではこういうことをやっていく」というような目的設定がプロジェクトごとに明確化されていて、それが少なくとも関係者に対しては納得されているわけで、よその街の人がそこに文句を言う必要はないと思うんですね。
ただ、実際ややこしいのは、そのプロジェクトに文化庁とかが関わってきたときに、今度は「それは国の金だ」と全国の人が文句を言えるような構図になってくる。基本的には「街のことはその街の人間が考えるべきじゃん」って言えばスッキリしてくると思うんだけど、その辺りの明確化がまだ足りていないんじゃないかなと思っています。
この本(『地域アート』)の中でも、アーティスト側は何種類かのレイヤーに分かれています。アートプロジェクトに関わると税金を含めたお金が入ってくるので、ある種の「アーティストの側がお金を確保するための手段」みたいなものに次第に成り代わっていった部分がある。その中で、「アートとしての強度」みたいなものが問われるよね、という話があって。一方で中堅から上ぐらいのアーティストの発言が出てくるんだけど、(地域アートプロジェクトだけじゃなくて)ギラギラしたアートマーケットのような作品を金銭に変換する現場を見ることも若いアーティストには必要で、そういう緊張感は地方では難しい、みたいな話にだんだんなっていって、地域アートプロジェクトの中で生まれる作品に対しての議論が尻すぼみしていくような印象を僕は受けたんですね。
アートプロジェクトを運営する側は、お金――税金・公金だろうが企業が作ったお金だろうが――に対してプレゼンテーションはうまくても、そこに向き合ってプレゼンで匂わせた成果に対して応えきれているのかといえば、総じて怪しい、というのが僕の率直な感覚だったりします。その点では、BEPPU PROJECTはメディア露出や広告効果みたいなことを言うことで、(ネガティブな見られ方を)ある程度回避したんだと思うんですけど。
アートプロジェクトの生む価値を周囲にどう説明するか
林:客席からも「アートが生むどんな価値が、誰にとっての何の役に立つのか、企業や行政の方にはどう説明していますか。具体的な事例をお願いします」という質問が出ています。
寺井:なるほど。どう説明していますか? アートの生む価値を。
林:先ほどの「評価の尺度はどこにあるのか」みたいな問題と同様に、言葉の橋渡しをどのレベルで行うかというマネジメントの問題になってくるんじゃないかと思います。基本的に民間企業はやりやすいですね。たとえばRelight Projectの場合、すごく細かい話ですが、作品が点灯されると電気代がかかる。その電気代や消灯/点灯の中での調整コストについてはあくまで、作品を所有しているテレビ朝日さんの立場を尊重した上で、こちらから1円もお支払いすることなく、全部向こうにやってもらっています。「テレビ朝日が協力している」ということを前面に出す形でなくて良ければ、ということにして。つまり、こちらがテレ朝さんに提示した再点灯のメリットというのは、「この地域の賑わいを取り戻す」とか「いろいろなことをする一つのきっかけになる」みたいなことだったんですけど。
寺井:それは、地域貢献とかそういう考え方に近いですか?
林:一つはそういうことだったと思うし、もう一つは、話をする中でテレ朝さんとしても「どのタイミングで点けようか」みたいなことを内部でも考えていたということがわかってきたので、「これを一つの節目にしませんか?」という側面もあったと思います。
一発でこのブリッジが掛かることはないから、いかに関係性が築けるかですよね。話をする相手が意思決定者だったらその場でOKと言ってくれるかもしれないけど、そうじゃないことがたびたびある。こっち側がいかにビジネスのロジックを使って話しても、その人が上の誰かにまた話さなきゃいけないし、そういうのって社内の政治や制度が関わってきたりするじゃないですか。
寺井:もちろんそうですね。
林:だから、相手との関係性の中で言葉を繋げていくというのが大事なんですよね。
行政相手に“寝技”を繰り出す
林:その反面、行政を相手にするのはやっぱり本当に難しいですよね。
寺井:難しいよね。
林:地域によってですけど、本当にどうしたらいいのかって思いますよね。
寺井:行政の人には、現実的にはどういう説明をしているんですか。何だかんだ、成果を問われるわけでしょ。
林:2009年の混浴温泉世界のときに、ジンミ・ユーンっていうアーティストが映像作品を作ったんですね。その作品では、アーティストが這うんですよ、別府のいろんなところを。最初に、別府公園内を這いたいという提案があって、そこに行って、這う・記録する……という。これは許可が必要だなと思って、(役場の)公園緑地課に行ったのかな。そこで概要を話して、「映像撮りますか?」と聞かれたので「撮ります」と言ったら「△△課の許可を取ってください」と言われて。その先で「這います」と言ったら次は「●●課に行ってください」と、一通りたらい回しにされて……何周かしたときに、商工課の課長さんがすごく理解のある人で、「話つけたる」と言ってくれたんです。なぜかその人が(別の課での許可取りに)立ち会いながら、「結局何をやるの?」「よくわからんが、街中を這うらしい」「そうかい」っていう、咬み合わない空気の中で許可をもらったりしたかな(笑)。多分その商工課の人も、もともとはその課にいたとかだったと思うんですけど。
寺井:今の話って、ある種の“寝技”というか……人間関係・信頼関係を作って話を通したというケース。相手側も、やらせてくれる技は一応持っているわけじゃないですか。行政の外にいる人が「やりたい」と言って、中にいる人が「やらせてやろう」という構図で話をすると急に通る、みたいなことは実際にいっぱいある。だから、ある意味“寝技”を決めまくってプロジェクトを実現できているという話でもあるなと思って。
それは、ディレクターやキュレーターのような実現をサポートする側の人からすると、ある種の奇跡を起こしたみたいなものなので、運営側のエクスタシーとして「やってやったぜ」ということも含めて成功体験になりがちだと思うんだけど、それは割と偶然性の高い“寝技”だったりすることが多いわけで。「それがこの先も同じように続くんですか?」という観点で見ると意外と続かなかったり、そういう闇は抱えているなと聴いていて思いましたね。
林:方程式はないですよね。方程式を探そうとして具現化させることができるのかというと、僕はできないんじゃないかと思っていて。ただ、もっとメタなところで“寝技”の考え方というか、組み方というか……「公園って正しい使い方はこうですよね」みたいな善か悪かみたいな話ではなくて、もうちょっと「こういうところのこのルールに関してはこう使えますよね」みたいな応用を考えられるんじゃないかな。
ふと思い出したんだけど、ライゾマティクスの齋藤精一さんと以前話したときに、彼は徹底して道路交通法を読み込んでいると言っていましたね。「街の中ではどこまでの表現がどの状況であれば許されるか」ということを、弁護士の意見を聞きながら、とにかく読み込んで具体的にどうすれば実現できるかを考えている、と。
寺井:映像とかプロジェクションをやっている人は気になるはずですよね。僕もそれはやったことがあります。“道路の上を光の粒子が通って”いるので、それは道交法違反だとか、すごい話があったりして。
林:その1点を押さえて、きちんと行政とは対話をしつつも、合理的なところだけで解決しないところもあるから、常に寝技を決められるような関係性を作るということですよね。
寺井:これは一つの答えじゃないかと僕は思っているんですが、アートプロジェクトと呼ばれるものを実現していくときに、運営している側もそういう“寝技”的なところで、アーティストと同じぐらい苦労しているじゃないですか、手前味噌的ですが。道路上を光が通るだけで道交法違反だと言われたとき、アーティスト的には「バカなんじゃないの」っていう受け取り方にしかならないんだけど、往々にして企画が実現できない本質がそこにあったりして、運営側はそこを何とかクリアして実現させている。だから意識としては「運営側もアーティストと同じように、その瞬間は“表現”をしている」と僕は思っていて、その満足感や表現欲でどこか頑張れているところがある。だから、アーティストとの関係性の中でそういう理解が揃っているんだったら、そのアートプロジェクトは成立する気がするんですよ。
アーティストとまちづくりが接近することの弊害
寺井:それって運営側とアーティスト側の信頼関係がお互い強固だからこそできることで、僕はそれが成立したら素晴らしいし、過去には成立したこともあると思ってるんだけど、一方で難しいのは、その関係が成立しないことも多かったり、年々成立しなくなってきている気もしているんです。
それを一番感じたのは、グラフィティの人とやっていたときですね。僕の前職の話だけど、夜中に描いてしばしば警察に捕まってというのをやっていたグラフィティの人たちに、昼間に合法的に描ける場所を用意したことがあった。そのことに対する、ある種の感謝のようなものはわかりやすかったんです。要は、彼らの力では絶対に実現できないことで、元は警察に捕まっていたようなことが捕まらなくなったというところがわかりやすくて。
そういうトレードオフのような関係があったんだけど、大量生産されているアートプロジェクトが示すように、まちづくりの人とアーティストが一緒に何かやればやるほど、まちづくりとアートのやっていることは近づいているんです。もともと「まちづくりの人ってワークショップやってるんでしょ」みたいな世界だったのが、今ではアーティストの人もワークショップを連発しているような状況もある。その何が難しいかと言うと、近づきすぎているせいで相手がしていることの貴重さが感じられなくなって、お互いに敬意が払えなかったり、信頼関係を築きにくくなっているんじゃないかなと。
林:そこで何かできるとしたら、やっぱりビジョンの共有でしょうね。コーディネートする側として示せるのは、アーティストへのリスペクトと、「あなたのこういう視点を必要としている」ということかなと思ってます。代案を出せないからアーティストを必要としているし、「あなたがいないと成立しない」ということをまずは示すべきなのかなと。
それから、まちづくりとアーティストの役割が近づいてきているという話ですが、アーティストが街でワークショップを実現するにあたって、ともするとアーティストもコミュニケーションや交渉力を磨いていかないといけないということになっていく。逆に、プロジェクトを企画する側も、場合によってはアーティストに(ワークショップの)プロトタイプを提案することができなければいけない時代ですよね。
寺井:実際、方向性としてはそういうことが起きていると思います。一方で僕はお互いが改めて役割分担を意識する方が結果的に一緒にやりやすいのかなとも思っていて。そうでないと、お互いに不幸になったり、全体のクオリティは落ちていく気がする。
[後編「『地域アート』って言われているものの正体って一体何なんだとずっと思っているんですよ。」に続きます]
撮影・構成・編集:後藤知佳(numabooks)
編集協力:吉崎香央里、松井祐輔
(2016年4月29日、FANCLUBにて)
【まちづクリエイティブ「アソシエーションデザイン」対談シリーズ バックナンバー】
▶寺井元一(まちづクリエイティブ代表取締役)+西本千尋(まちづクリエイティブ取締役、ストラテジスト)+小田雄太(まちづクリエイティブ取締役、アートディレクター):
「アソシエーション」と「コミュニティ」をつなぐやり方――『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『山田孝之の東京都北区赤羽』から読み解く「まちづくり論」。
▶まちづくりとアート│01
池田剛介(アーティスト)+寺井元一:
アートと地域の共生をめぐるトーク
▶まちづくりとアート│02
大山エンリコイサム(美術家)+寺井元一:
ストリート・アートと公共性 ――表現の自由論からコレクションによる歴史形成まで













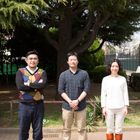











COMMENTSこの記事に対するコメント